「さて、これから一気に10年歳月が流れる。王妃とそれを取り巻く環境も大きく変わる。」
美穂が戻ってくると僕は話を再開した。
「10年経つと王子も颯太よりちょっと上くらいの年齢になるわよね。王妃はアラフォーに差し掛かった
くらいかしら。」
「大体、そんなイメージで考えてくれていいよ。」
美穂は酔いながらも、物語のディテールを思い浮かべ始めていたようだった。
「最初に言ったように王子が生まれてからは、王も持ち前の野心がすっかり影を潜めておとなしくなっててしまった。それで他国との争い事が無くなってきたのは良かったんだけど、同時に国政にも興味がなくなって、ほとんど宰相に任せっきりにして遊び呆けるようになってしまった。でも元々国自体は領土も広くて交易で栄えていたから、実は特別な事をしなくても安泰だった。ひどい話だけど小さな国に戦争を仕掛けたのは、ほとんど王のエゴだったんだよ。」
「きっと飽きっぽい性格だったのね。そういう人がいるといつも周囲の人間が振り回されるのよ。特に上司がそうだと本当に厄介。」
「そうだね、それに誰よりも苛立っていたのは王妃だった。宰相に国政を任せていたとはいえ、最終的な決定には国王の決裁が必要で、それを代理で王妃がおこなっていた。来賓のおもてなし、国内の紛争の仲介役、家臣の評価と報酬額の算定等やることは山積みだった。でも国政の仕事自体、王妃は嫌いではなかった。社交的な性格だったから外交もむしろ楽しんでやっていた。だから苛立っていた理由は別にあったんだ。」
そこまで話してから僕は続けるのを躊躇した。
「何で急に話を止めるの?別の理由って何なの?」
僕はこの後の美穂のリアクションが怖かったので話を止めたのだが、やむを得ず話を続けた。
「それは王が妾を作っていた事なんだ。それも一人じゃなく、何人もだ。王はその頃、気に入れば使用人の娘でも見境無く手をつけるようになっていた。村人達はそれを知って、できるだけ器量良しの若い娘を宮中で働かせて王に取り入ろうとしていた。それが王妃の怒りを買っていたんだよ。」
僕がそう言うと美穂はいきなりワインの小瓶を勢いよくテーブルに「ドン!」と置いて腕組みをした。どうやら美穂の琴線に触れてしまったようだった。
「はぁ?妾?そりゃ王妃からしたら溜まらないわ。仕事は押しつけられるわ、旦那は若い女と遊び呆けてるんじゃ。ところでシュン、あなた颯ちゃんにこんな話をするつもりだったの?妾なんて一体どういう説明をするつもりなのよ?」
美穂はよほど興奮していたのだろう。「シュン」と呼び捨てにされたのは、本当に久しぶりの事だった。物語の背景として妾のエピソードは必要だったので省略するわけにはいかなかったが、僕は美穂に話してしまった事を後悔した。
「ち、中世ではそういうことが当たり前だっただろ?昔の権力者っていうのはそういうものだったんだよ。それと颯太に話すときは当然、別バージョンにするつもりだからさ、心配しなくても大丈夫だよ。」
「当たり前よ、颯ちゃんには絶対にしないでよね。まぁ物語の背景として必要なら仕方がないけど。韓流ドラマの歴史物でも妾の話なんてよく出てくるしね。」
美穂はそう言って、少し冷静になってくれたようだったので、僕は胸を撫で下ろした。
「それで?どうなったの?」
「うん、その諸事情があって王と王妃の関係は徐々に険悪になっていった。この先は会話形式で話をするけど、いいかな?」
美穂が頷いたので僕は話を続けた。
その日、王は久しぶりに王宮に顔を出し、王座に鎮座していた。なぜだか手持ち無沙汰な様子で座っているその姿を見て、王妃は薄笑いを浮かべ話しかけた。
「あら珍しいこと、この国の王様はてっきりご隠居なさっているとばかり思っていましたわ。今日は何の御用かしら?」「それは、ご挨拶だな。俺は隠居した覚えなんか無いんだがな。まぁ、たまにはこの国の本当の主が誰かを教えてやらんといかんと思ってな。」
王も王妃の嫌みにはすっかり慣れていたので、軽い口調で言葉を返した。
「そういうことは、やるべき事をなさってから仰ったらどうかしら。あらかた若い娘でも物色なさりにいらしたんじゃない?そちらの方は相変わらずお盛んなようなので。」
すると王は少し苛立ち、王妃を威嚇するかのように立ち上がった。
「お前は大きな勘違いをしているようだな。王の役割とは一体何だ?国政も外交も確かに必要だ。でも俺くらいの年齢になると後継者作りが重要になる。より優秀な遺伝子を引き継ぐ者を作らねばならん。そんな事はどこの国の王でもやっている事だ。」
「ふん、物は言いようね。でも後継者ならすでにヒソップがいるでしょうに。他に跡継ぎなんて必要ないんじゃなくて?」
ヒソップは10年前に生まれた王子の名前だ。王妃は王の威嚇にも怯まず、悠然と答えた。
「あいつには残念ながら王としての資質がない。槍を持たせても馬に乗らせても不器用で、一向に上達する見込みが無い。かといって頭の回転が速いわけでも無く、社交性にも乏しい。素直に言うことを聞くのは良いところだが、気力、胆力には欠けている。まだ、前の王のくそ生意気な王子の方が気骨があった。俺に逆らうぐらいがちょうど良いんだ。もっともあいつは可哀想な事になってしまったがな。」
王妃はそれを聞いて眉をつり上げ地団駄を踏んだ。自分の息子の事をあからさまに誹謗する王のことが許せなかった。
「あの子のことを悪く言わないで。今は確かに頼りない所があるけど、これから私が立派な王に育て上げてみせるわ。」
王妃は王をキッと睨みながらそう言ったが、王は怪訝な表情をして首を左右に振った。「いや、お前はもうヒソップには関わらなくていい。あいつはお前の言う事には、素直に従っているようだが、何でもかんでも押しつけるからすっかり萎縮して自分の意思というものを持てなくなっている。厳しく躾けているようで実は甘やかしているのも同じだ。だから俺が、とびっきり優秀な教育係をつけてやることにした。今日はその話をするために来たんだ。」
王のその言葉に王妃は更に激高した。
「解ったような事を言わないで!教育係ですって?今まで散々放ったらかしにしておいて、どの口がそんな事をいえるの!」
「口の聞き方に気を付けろ。例え王妃でも俺を侮辱する奴は処刑することもできるんだぞ。」
王も王妃の言い方が癇に障ったのか感情を抑えきれなかった。
「やれるものならやってごらんなさい。私がいなくて、この国を治められるとでも思っているの?それに国政なんか始めたら、大好きな若いお嬢さんと夜遊びする時間もなくなるわよ!」
それからしばらくの間、お互いに沈黙したままの睨み合いが続いたが、王はこれでは話し合いにならないと思ったのか、少し優しい口調で王妃に語りかけた。
「なぁ、デイジー、少し冷静になろう。俺も少し言い過ぎた。お前はよくやっている、それは認めるよ。でもな、お前は今、すっかり疲れ切っていて以前の溌剌さや愛らしさが無くなってしまっているよ。やっぱり女は国政なんかに関わるもんじゃないな。そうだ、少し外遊にでも出てのんびりしたらどうだ?新しい黒船と俺の精鋭の親衛隊を貸してやる。ヒソップの事はそれから改めて考えようじゃないか。」
デイジーというのは王妃の名前だ。それは王妃にとってはとても屈辱的は言葉だった。「それは何の戯言?私をこうさせたのは誰のせいなの?それに私は外遊なんかに行かないわよ。ヒソップと一時でも離れて暮らすなんて考えられないわ。」
王妃は涙目になりながら、王に訴えた。
王妃の言葉を聞き、王は深いため息をついた。それから王座の横にあった剣をゆっくりと持ち上げ、王妃に向かって突きつけた。
「いいか、これは王命だ、外遊に出ろ。背く場合は反逆罪と見做す。話は以上だ。」
王はそう言い残して宮廷を後にした。
残された王妃は、言い返す言葉も無くただ呆然とその場に立ち尽くしていた。その夜、王妃は王子のヒソップを自分の部屋に呼び、外遊に出る事を告げた。
「ヒソップ、母様はしばらくの間、お仕事でお城を留守をする事になったの。だからその間は、父様と教育係の言う事を良く聞いて勉学と武術に励みなさい。」
それを聞いたヒソップは動揺し、悲痛な表情を浮かべた。
「母様、何処かに行ってしまうの?しばらくの間っていつ帰ってくるの?ねぇ、それなら僕も一緒に連れて行ってよ。僕はあの教育係はなんだか陰湿で嫌いなんだよ。」
王妃はヒソップの言葉に苛立ったが、極力顔に出さないように努め優しい口調で語りかけた。
「情けないことを言わないで。あなたはいずれこの国の王になるのよ。今は辛いかもしれないけど辛抱して言うことを聞いていなさい。」それからヒソップは、泣きじゃくりながら王妃にしがみついてきた。王妃はヒソップを抱きしめて慰めながらも、癪なことに王子の持つ気質については王の言った事を認めざるを得ないと思っていた。同時に今、自分が発した言葉には既視感を感じた。
「私はまた同じ事を繰り返している。今度はうまくやれるのだろうか…。」
王妃はヒソップに、かつてのアリゼの姿を重ねずにはいられなかった。
「こうして王妃は外遊に出されることになった。表向きの理由は近隣諸国との外交のためだったけど、実際は、体の良い厄介払いだった。」
「それから王妃はどうなったの?どこに行ったの?」
美穂は王妃の行く末を案じているようだった。
「王の言う通りに外交する気分にはとてもなれなかったから、初めは漠然と近隣の海をただ周回していた。でも思い悩んでいるうちに、ふと以前暮らしていた小さな国、【お国】に行こうと思いついた。」
「だけど、戦争で焼け野原になっちゃったんでしょ?行ったところでどうしようもないじゃない。」
「実は【お国】は王妃の生まれ故郷だったんだ。元々は貧しい農家の生まれだったんだけど、王様に見初められて王妃にまでしてもらった。だから【お国】には愛着があったんだよ。これまでは過去のことは一切忘れようとしていたから、考えもしなかったんだけどね。」
「ふーん、そんなもんかな。私だったら故郷がそんな状態だって知っていたら見たくもないけど。」
美穂は少し否定的な見解を持ったようだったので、僕は心情を解ってもらえるように説明をした。
「それは人それぞれなんじゃないかな。王妃なりに切羽詰まった状況になっていたから、何か心の拠り所になるものが欲しかったんだよ。」
「まぁ、いいわ。話の輿を折っちゃってごめんね、続けて。」
「うん、それで家臣に命じて【お国】に向かわせることにした。もちろん家臣一同は状況を知っていたから猛反対したけどね。それでも王妃の意思は固かった。」
「王妃が悲しむ結果にならなきゃ良いけどね。」
美穂はテーブルに両肘をついて淡々と語った。
その時、iPhoneの液晶には21:42と表示されていた。ここまで話してきて、ようやく物語の背景が見えてきた気がした。僕は美穂の言葉に頷きながら、次の展開を考えた。


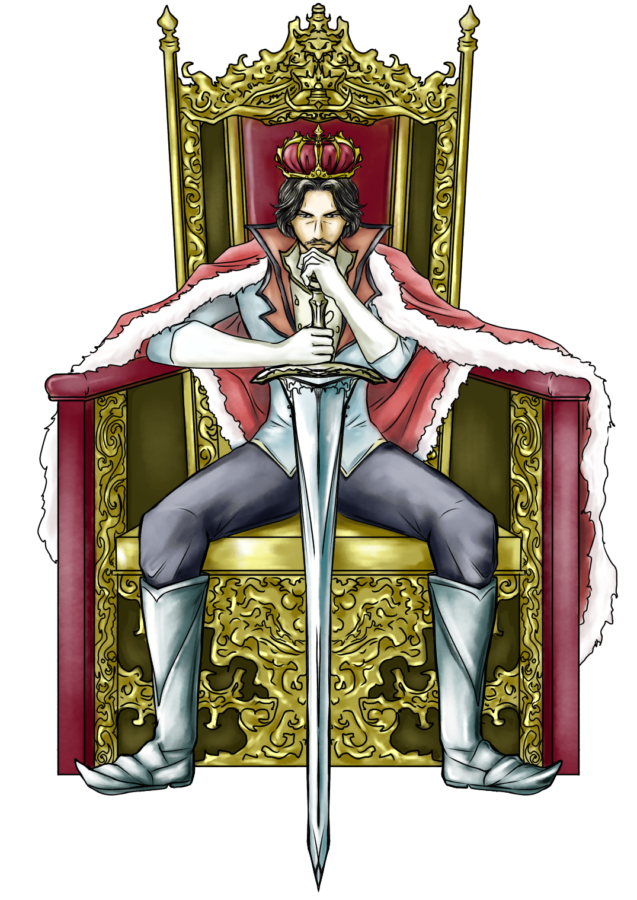
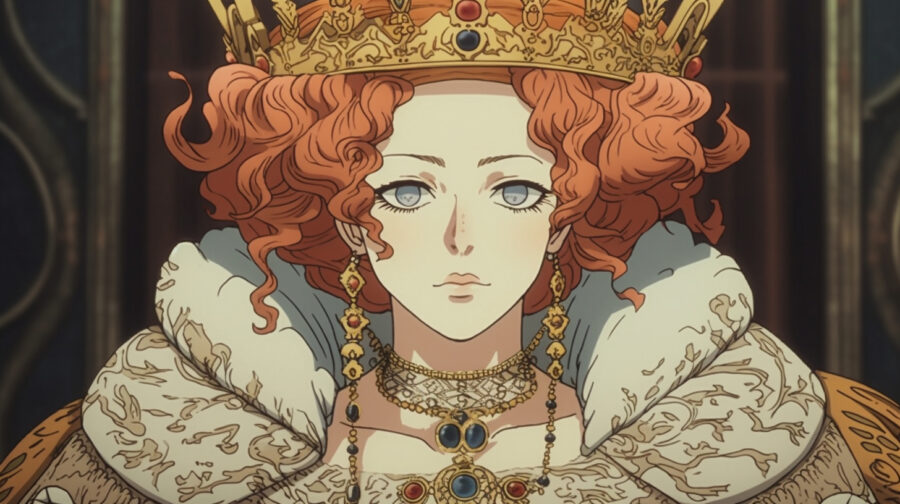
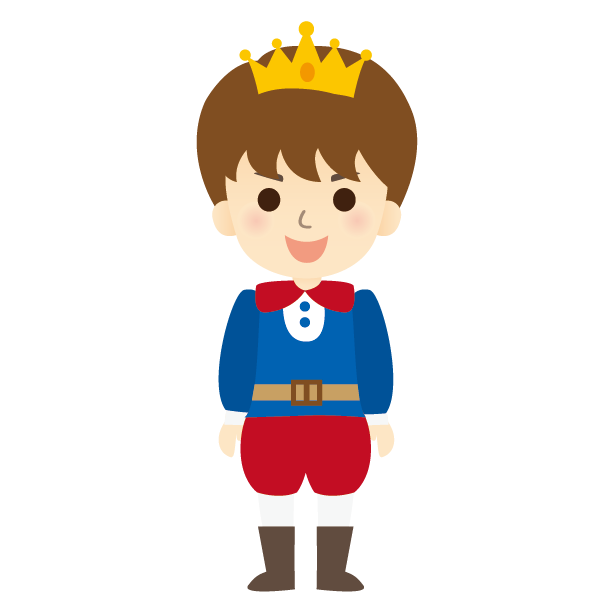


コメント