その夜、僕は久しぶりにやんちゃな王子の夢を見た。それはアリゼがちょうど、島の監視員の仕事に就いて兄との再開を果たした頃の話だった。
アリゼは思いがけず兄との再開を果たした後も、島で海の監視員の仕事を続けていた。その日もいつものように入り江に小舟を出して巡回をしていると、外海との境界辺りに見知らぬ黒船が停泊しているのを発見した。黒船が島からあえて離れた場所に停泊していた事にアリゼは違和感を感じた。それから注意深く近づいてその船をよく見てみると、真新しくフレームの金属部分には錆一つ無い新しい船だという事が解った。漆黒の船体は日の光を受けてまばゆく輝いていた。
「こいつは、ひょっとしたら最新型じゃないか?」
アリゼが直感的にそう思っていると、甲板の上にはいつの間にか上品なスーツを着た年配の紳士が立っていた。彼は杖をついて遠眼鏡のようなものを持ち、アリゼの方を凝視していたが突然【お国】の言葉で話しかけてきた。「やぁ、ご機嫌よう。君はあの島の人間かね?私の言葉は理解できるかな?」
年配の男のようだったが、その割にはよく響くオペラ歌手のような声だった。アリゼは馴れ馴れしく話しかけてくる紳士を不信感を持った。そもそもスーツを着た人間が黒船に乗っている事自体、不自然に感じた。
「言葉は解るよ。それよりおじさんはこんな所で何をしてるんだい?パーティ会場はこの辺りには無いよ。」
アリゼがそう言うと、紳士は大声で笑い出した。
「はっはっは、そうだな、残念ながらパーティーにはもう間に合いそうもないな。うん、君にはなかなかユーモアのセンスがあるね。真面目な話、嵐に遭ってしまってね、それを避けながら舵を取っていたら、この海域まで流れて来てしまったんだ。座礁こそ免れたがその時にずいぶんと燃料を使ってしまったから、身動きが取れなくなってしまったんだ。」
「それはお気の毒だったね。でもこの島では石炭は採れないからおじさんを助けることはできそうもないな。石炭はもう全然残ってないのかい?」
「いや、最低限は残してあるんだが、なるべく節約したいんだ。何しろ長旅なんでね。そこで相談なんだが、もし薪があったら少し譲ってくれないか?」
薪?そういえば非常用の燃料として石炭の代用品になると聞いたことがあったな。アリゼは不意に【お国】にいた頃に家庭教師から教わった事を思い出した。
「薪なら島に戻れば少しは都合がつけられるよ。それより何処まで行くんだい?」
「オグロマン国だ。外遊に出て祖国に帰る途中だったんだ。」
「オグロマン?聞いたことが無いな。」
「最近、独立したばかりの新しい国だからね、知らないのも無理は無い。それでも見ての通り黒船も持っているし、それなりに栄えている国だ。お礼は弾むからお願いできないか?金貨とそれに上等の葡萄酒、コショウと葉巻もつけるよ。」
「そんなにたくさん?こちらからは本当に薪だけでいいのかい?」
「ああ、構わない。私は祖国に無事に帰れさえすればそれでいいんだ。」アリゼは紳士の言葉を完全に信用した訳ではなかったが、いつの間にか手助けをしたくなっていた。その紳士と話をしているうちになぜだか好感を持つようになってきたからだ。そして何よりも報酬が魅力的だった。それからアリゼは一度島に帰り、バハリに家にある薪を使わせてくれないか頼んでみた。
「薪だって?何に使うんだ?」
アリゼは経緯をかいつまんで説明したが、バハリは首を傾げた。
「どうも腑に落ちないな。薪が非常用の燃料に使える事は知っていたが、かなりの量が必要になるはずだ。それに近くには石炭を売っている国もあるはずなのに…。」バハリは少し不信感を持ったようだが、アリゼは説得を試みた。
「その辺の事情は解らないけど、もう本当に燃料がぎりぎりなんじゃないかな?でも、悪そうな人には見えなかったよ。それに騙そうと思っているなら薪なんかじゃなくもっと違うものを要求してくるんじゃないかな?何よりも本当に困っているなら見過ごすわけにはいかないだろ?」
「うーん、まぁそういうことなら構わないが、充分気を付けろよ。お前にはどうも迂闊なところがあるからな。」
「解ってるよ。心配性だな、バハリは。でも、薪だぜ。万が一持って行かれたって、大して損はしないよ。それにこの取引を成功させれば俺も兄さんほどじゃないにしろ、もっと認められるようになるだろ。まぁ、久しぶりに上等の葡萄酒を飲ませてあげるから楽しみにしてなよ。」
そう言ってアリゼは、家に備蓄してあったものと近隣の人に頼み込んで貰った薪を荷車に積めるだけ積み込んで港へ向かった。港に着くと役場勤めで知り合った友人のタフラがいたので声をかけ、薪を小型の帆船に積み込む作業を手伝って貰った。
「あの沖の方に見える黒船かい?イルファンの船よりは小さいが、なかなか良さそう船だな。」
タフラは手をおでこに当て日差しを遮りながら、沖合の黒船をしげしげと眺めて唸った。
「そうなんだ。しかも最新型で船体はピカピカだ。おまけにスーツを着たおっちゃんまで乗ってるんだよ。船の中はどんな風になってるのか見てみたいもんだ。」「おいおい、あんまり変な事は考えるなよ。バハリの言うとおり、ちょっと不可解なところもあるしな。」
「大丈夫だよ。貰うものだけ貰ってとっとと帰って来るから。」
アリゼはそう言って薪を帆船に積め終えると沖の方に向かって船を漕ぎ出した。「おーい、おじさん、薪を持ってきたよ。」
黒船に近づきアリゼが声をかけると先ほどのスーツを着た紳士が甲板からひょっこりと顔を出した。
「よく来てくれた。今、荷台を下ろすからそこに薪を積み込んでくれないか?」
「それはいいけど結構重いぜ?引き上げられるのか?」
「ウインチにエンジンを連動させて巻き上げるから、少しくらい重くても大丈夫だ。」
紳士はそう言って荷台をスルスルと下ろしてきたので、アリゼはその上に薪を積み込んでロープでしっかりと固定した。
「いいよ、引き上げてくれ。」
アリゼがそう言うと、荷台はみるみるうちに引き上げられて甲板まで辿り着いた。
「やっぱり、この船のパワーは凄いや、半端じゃない。」
感心して見上げていると甲板には作業員が複数いるのか、あっという間に空になった荷台が降ろされてきた。それを数回繰り返し、全ての薪を荷台に乗せ終えて一息ついていると、また空になった荷台が降ろされてきた。アリゼは甲板を見上げて叫んだ。「おじさん、今ので最後だ。もう薪は無いよ。」
すると紳士は甲板から身を乗り出すようにして叫んだ。
「ありがとう。それじゃあ、お礼を渡したいので甲板まで上がって来てくれないか?荷台に乗ってくれれば巻き上げるから。」
「え、それは遠慮しておく。お礼は荷台に乗せて降ろしてくれればそれで構わないよ。」
「いや、できれば直接会ってお礼が言いたいんだ。私を信用してくれているのなら上がって来てくれないかな?そもそもこんな年寄りに悪さなんかできないと思わないか?」
紳士は笑いながらそう言った。アリゼは少し躊躇したが、それでも最新式の船を見てみたいという好奇心に駆られ、荷台に乗った。帆船は動かないように黒船のフックにしっかりとロープを結んで固定をしておいた。それから荷台は引き上げられ、甲板の高さまでくると紳士は満面の笑顔を見せてアリゼを出迎えた。紳士は思った通り、初老の男だった。今まで力仕事などしたことがないのだろうか?背は高かったが、色白で痩せており柔和な顔をしていた。髪はグレーに染まって口髭までたくわえており、いかにも育ちの良さが垣間見えた。紳士は白い手袋をした手を差し伸べてくれたので、それにつかまり甲板に登った。甲板は真新しい樫の木で作られ、汚れ一つ無く磨かれており、この船が建造されて間もないことがよく解った。
「よく来てくれた。本当に助かったよ。それと君は思ったより若いな。それに島の原住民でも無さそうだ。なんでこの島に住んでいるんだい?年は幾つくらいなのかな?」
矢継ぎ早に質問をしてくる紳士にアリゼは苛立ってこう言った。
「自分の年なんてこの島に来てから忘れちまったよ。それと人には色々事情ってもんがあるんだ。初対面でそういう事を聞いてくるのは失礼だぜ。」
「はっはっは。これは申し訳ない。君の言う通りだ。私は年の割に好奇心が旺盛でね。どうか気を悪くしないでくれたまえ。君の事を聞くのはまた次の機会にしよう。」
次の機会って?何のことだ?アリゼが紳士の言った言葉の意味を考えていると、使用人らしき者が現れ、布袋一杯の金貨と葡萄酒の大きな樽を持ってきた。みなアリゼと同年代の若者達で身綺麗な服装をしていた。その所作の良さから高い教育と訓練を受けているように思えた。「ありがとう。これはささやかだがお礼だ。受け取ってくれないか。」
アリゼはその量の多さに目を丸くした。「おじさん、いくらなんでもこれは貰いすぎだ。本当にいいのかい?」
「ああ、構わないよ。ただ申し訳ないが、薪をもう少し貰えないか?それと新鮮な果物も食べたい気分なんだが、一緒に頼んでもいいかな?」
「お安い御用だ。でもまた薪を集めるのには少し時間がかかりそうだ。2、3日待てるかな?」「ああ、急ぐ旅ではないのでそのくらいなら待てるよ。よろしく頼む。」
紳士はそう言って、手を差し伸べてきたのでアリゼも恐る恐る手を差し伸べ握手をして船を後にした。アリゼは思いがけない報酬を貰った事で意気揚々としていたが、港に帰る途中に何か不思議な違和感を感じていた。「あの船の所有者は絶対に身分の高い貴族か王族の人間だ。それに船にいる間、常に誰かに見られていた気がする…。」
それから紳士は、マストの裏側に隠れていた人物に厳かに声をかけた。
「どうやらお探しだった子は、あの子で間違いないようですな。これで満足されたでしょう、奥様。さあ国へ帰りましょう。あまり長くいるとあらぬ疑いをかけられます。」
「そうね。でもできれば一度だけでもあの子と会って話がしたい。それは贅沢な願いかしら。」
紳士はその問いに対しただ首を振り、何も答えられぬままその女性のいる方を見つめていた。

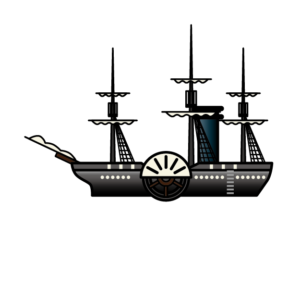
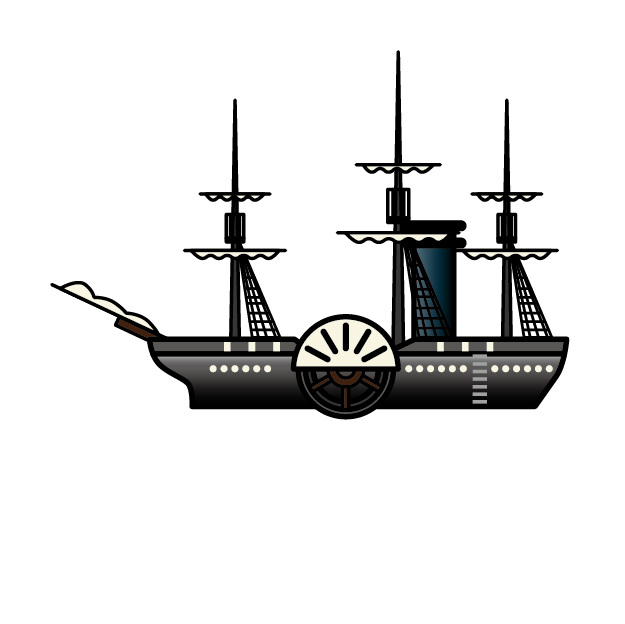







コメント