「まあ座れよ。本当によく来てくれたね。まずは乾杯しよう。」
そう言ってアリゼは僕に木を丸く削って作った器に白濁色の酒を注いで渡してくれた。
「これは例のお酒かな?」
「そうだよ。バハリが作った自家製の酒だ。といっても実際は君が考えたものだけどね。」
それから僕たちは杯を掲げて乾杯した。バハリの酒は熟成されたココナッツの甘さと柑橘系の果物の酸味が調和していてとても美味しかった。爽やかな香りが僕を心地よく刺激した。島のシュロの木は僕の予想を超えて大きくそびえ立ち、強い南国の日差しを見事に遮っていた。寝そべって目を閉じると潮風が名も知らぬ草花と土の香りを運んできた。こんなところで生まれ育ったら、あるいは僕は今とは全く違う人生を過ごしていたんじゃないか、そう思った。「シュン、もっとリラックスしていいんだぜ。なんといっても君はこの世界では創造主だ。この島の一等地にタワマンを建てることだってできるし、一瞬で水没させることだってできるんだ。ああ主よ、われらが人に赦す如く、われらの罪を赦し給え。」
茶化すようアリゼが言ったので、僕はため息をついた。
「アリゼ、僕は創造主なんかじゃない、だたの作者だ。例えばこの島にタワマンを建てるとしたら、誰が何の目的で建てるのか?その費用やら資材は誰が用意するのか?そもそも、そんなテクノロジーをどこで学んだのか?そこまで考えなきゃならない。そんな面倒な事をするくらいなら、初めから書こうとは思わないね。」
「なるほど、創造の世界ですら制約が沢山ある。作者ってのは意外に不自由なもんだな。」
「ところでアリゼ、ここは君が島の子供達と喧嘩をして派手にやられてルイカに手当をしてもらったところだよね。」
「そうだね、今考えてみると恥ずかしい思い出だ。でもおかげで僕はルイカと打ち解ける事ができた。ただ、その時は繋ぐ者っていう言葉の意味はさっぱり解らなかったけどね。」
アリゼがそういうとルイカがクスクスと笑った。
「あの時のアリゼは口をぽかーんと開けて、驚いた顔をしていて可笑しかったわ。」
「でもさ、いきなり繋ぐ者だなんて年端もいかない子供に言われても、何の事やらだろ?」「そうよね、でも実は私もその言葉の本当の意味は解っていなかったと思うわ。ただ決められた役割を果たしていただけ。もちろん、あなたと初めて会ったときに感じた直感のようなものは信じていたけれど。あれは私にとって忘れられない素敵なエピソードになったわ。特に『フクシュウはフクシュウしか生み出さない、センソウとおんなじ。だれもシアワセにはならない。』って言葉は今でも大好きよ。」
ルイカがそう言ってくれたので、僕は嬉しくなった。
「ありがとう、ルイカ。僕もあの台詞はお気に入りなんだ。君の人となりをよく表してるよね。」
「ところで、私の繋ぐ者としての役割はもう終わったの?私はこれからアリゼと一緒にアイニを育てながら家族で月並みな人生を過ごしていけばいいのかしら?」
ルイカのその言葉に僕は首を振った。
「ルイカ、君の繋ぐ者としての役割はまだ終わっていない。アリゼは知っての通り、根っからの風来坊だ。君が繋いでいてくれないと、糸の切れた凧みたいに何処へ飛んでいくか解らない。だから彼がしっかりとこの島に根を下ろすまでは見守り続けていて欲しいんだ。」
「そうね、確かにこの人はいつまでもやんちゃで、不安定なところがある。家族のためにも私はこれからも繋ぐ者でいなくちゃね。」
「ははは、僕はまだまだ信用が足りないんだな。でもまぁ自覚はあるよ。それに僕がそういう役割でないとこの物語は盛り上がらなくなるからね。ルイカ様、どうかこれからもよろしくお願い致します。」
アリゼがそう言って西洋式のお辞儀をすると、ルイカは「仕方ないわね。」という感じの笑みを浮べた。「なぁ、シュン。俺をメインにした話はないのかい?これから恋人や家族を作る予定は?」
それから突然、タフラが質問をしてきた。
「悪いけど今のところ、その予定はない。でもタフラ、君はアリゼの唯一無二の友達で重要な役割を果たしている。それだけじゃ不満かい?」
「不満じゃ無いけど、なんていうか俺の存在意義って何だろうって色々考えちゃう訳さ。」
僕はタフラを慰めたが、それでも不満げな表情でブツブツとつぶやいていたので、アリゼは思わず吹き出した。「ははは、なんだか君への質問コーナーみたいになっちゃったね。」
「まぁ仕方ないんだろうね。僕には作者として答える義務があるんだろう。」
「ところで、僕はこれからどうなるんだい?」
アリゼがそう言ったので、僕は率直に返答した。
「アリゼ、君は僕の分身であり、憧憬の象徴なんだ。この物語では僕ができなかったことを君に代わりにやってもらった。おかげで僕の中にあった心の澱のようなものを洗い流すことができた気がしている。だから君にはこれからも無邪気でやんちゃな存在でいて欲しいんだ。」
僕がそう言うとアリゼは少し寂しそうな表情を浮べた。「シュン、君が僕に何を期待しているのはわかる。フィクションの役割って多かれ少なかれそういうものなんだろうね。ただ、君には君の世界で実体験としてやりたい事はないのかい?」
不意にアリゼにそう言われて、僕は戸惑った。
「うーん、今は何も思いつかない。ただ美穂と颯太がいてくれて、今の生活がこのまま続いていけばいいかなと漠然とは思っているけど…。」「ふーん、まぁそれは解らないでもないが、ただ今の生活がずっと続いていくとは限らないものだ。君達の世界には、時間という概念が存在している。そして時代とともには環境も変わっていくから、常にその変化にも対応していかなければならない。君も変わっていかなければ、大切な家族を失ってしまうかもしれないよ。」
アリゼのその言葉に僕は苛立ち、そしてこう言った。
「いや、決してそんな事にはならないし、させない。家族の絆っていうのは、そんなに簡単に切れるものじゃない。一般論で僕の家族を語らないで欲しい。」
「シュン、人は変わっていくものだよ。美穂や颯太もそれは同じだ。変わらないのは僕達のようにおとぎ話の世界に生きている人間だけさ。君達が生きている世界はとても複雑で、争い事が絶えず、常にアップデートされ続けている面倒な世界だ。ただ、その代わりにこの世界にはない温かみもある。老いや死の存在があるからこそ、人生が尊く感じられるんじゃないか?それは僕達には永遠に解らないものだ。同情もするが羨ましくもある。家族のためにも枯れるなよ、シュン。」
そのアリゼの言葉をきっかけに、僕は突然強烈な睡魔が襲った。急速に意識は遠のき、目を開けていることもできなくなった。「そろそろだね。」
「そうだね。」
アリゼとタフラの声が聞こえてきた。
「なぁアリゼ、例えばシュンを帰さずにここでずっと一緒に暮らすっていうのもありかな?」
「タフラ、君は時々、とても残酷なことを言うね。」
「いや、そうかもしれないけど、よほど強い思いがないとシュンはここには来られなかったと思うんだよな。それだけ今の世界から逃避したいと思っているんじゃないか?」
「いや、そうじゃない。シュンは美穂と颯太の所に帰りたいと思っているはずだ。今は彼は、きっと混乱しているだけなんだよ。いずれ気持ちも落ち着いてくるだろう。」「そうね。シュンを無事に帰してあげましょう。それとここに来るのはリスクが高いから、これで最後にしてあげないとね。」
ルイカの優しくて温かみのある声が聞こえた。
「そうだね、ルイカ。それとシュン、まだ僕の声は聞こえているかい?最後に君にお願いがある。僕の母様の事をあまり悪者にしないで欲しいんだ。あの人は確かに周りの人間を深く傷つけてきた。しかもその事に無自覚なまま自由奔放に生きてきた。決して褒められた事じゃない。でも同時にその事で周囲の人間に誤解され、疎まれ、悩み苦しんできた。茨の道を生きてきたし、その報いも受けてきたはずだ。もう、そろそろお互いに許してあげないか、母様達のことを。それに僕はもうあの人を恨んではいない。君だって本当はそうなんだろう?ただそれを認めたくないだけなんじゃないか?」「それと君は気づいているか?いつまでも心の呪縛を抱えたままでいる自分自身のことを。美穂と颯汰はいつもその事を心配している。大切な家族を不安な気持ちにさせるのは良くない事だ。君はこの物語を通してそれを僕に教えてくれたじゃないか。早く解放の呪文を手に入れるんだ。そのためにまずやることはこの物語を完成させることだ。美穂と新居やNISAとやらの話をするのはその後でもいい。さよなら、シュン。もう君にここで会うことはないだろう。それでも僕達はいつまでも君とともにいる。呪縛から解放された君が人生というストーリーをどうやって生きていくのか楽しみに見守っているよ。」
聞き取れたアリゼの声はこれが最後だった。やがて深い暗闇が訪れ、無数のとても細かい光の粒子が僕の体を幾度も幾度も高速で貫いていった。さよなら、アリゼ、ルイカ、タフラ。南国の日差し、潮風に揺れるパームツリー、時間の概念のない、永遠のイノセントワールド。
「大丈夫ですか?私の声が聞こえますか?」
突然、声をかけられ目が覚めた。頭がズキズキと痛み、まだ自分の体がまだ宙に浮いているような違和感があった。
「ここは何処ですか?」
「市ヶ谷の駅前です。あなたはここで意識を失っていたんですよ。自分のお名前が言えますか?」
僕は自分の名前を告げた。目を開けるとそこにはスーツ姿の若い女性が身をかがめて立っており、僕を心配そうに見つめていた。
「意識が戻って良かったです。気分はいかがですか?今、救急車を呼びますから。」
女性がそう言ったので、僕は慌てて首を振った。
「いえ、少し疲れが溜まっていて寝込んでしまっただけなので、大丈夫です。」
「え、本当に大丈夫ですか?少し頭も打っているようですが。」
僕は自分の頭を触ってみた。確かにおでこには瘤のようなものがあり、切り傷があるようだった。おそらく旅行代理店のウィンドウに頭をぶつけて気絶をしていたのだろう。正直なところ、あまり気分は良くなかったが、美穂や颯太に心配をかけたくなかったので、救急車は丁重にお断りをした。
「本当に大丈夫です。少し休めば回復すると思います。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。」
女性は少しの間、迷っていたようだったが僕が、自力で立ち上がったのを見て安心したようだった。
「…解りました。でも、怪我の治療は早くしたほうが良いですよ。お大事にしてくださいね。」
「そうします。本当にありがとうございました。」
お礼を述べると女性は、笑顔で頷き立ち去っていった。それから僕は駅前の薬局で絆創膏と頭痛薬とミネラルウォーターを買い、近くにあった公園のベンチに座り休んだ。まずはハンカチを水道で濡らし、傷口を拭いた。少し血の跡は残っていたが幸い、軽傷で傷口はもう塞がっているようだった。ただ頭痛がひどく、歩くたびに足下から錐で刺されたような激痛を感じた。
手探りで絆創膏を頭に貼り、頭痛薬を飲んでからiPhoneで時間を確認してみたが、まだ夜の8時過ぎだった。薬局に行って治療に要した時間を逆算すると、おそらく僕があの旅行代理店の前にいた時間は15分に満たなかったようだ。アリゼ達は僕をなるべく元いた正確な時間と場所に帰そうと配慮してくれたのかもしれない。あれが実際に起きた出来事であればの話だが。
薬が効いたのか、少し頭痛が治まってきたので、僕は市ヶ谷の駅まで行き、南北線で埼玉方面の電車に乗り帰路についた。幸いな事に電車は空いてたので、座って帰ることができた。その間に僕はSNSで美穂にこれから帰ることを告げた。地下鉄の中で、目を閉じてうつらうつらしていると、アリゼ達のいた世界から戻って来るときに見た暗闇と光の粒子が残像となって僕の頭を通り過ぎていった。



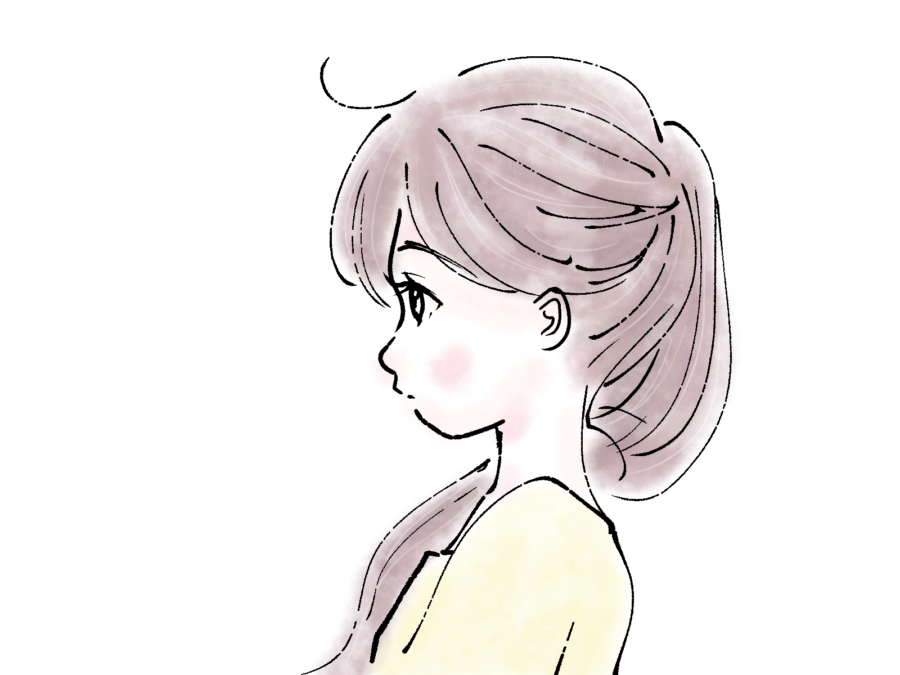




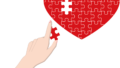
コメント