母が危篤になったと兄から電話があったのは、お正月休みが過ぎてすぐのことだった。僕は、ちょうど会社に行く準備をしている所だった。
「シュン、いよいよあの人が危ないそうだ。すぐ来られるか?」
「ああ、ちょうど出勤前で出かける準備をしていたから1時間もあれば行けると思う。」
「解った。じゃあ、現地で会おう。」
「ちょっと待って。マサ兄、どんな状態なの?もう意識がなくて話も出来ないの?」
「正確に言うと、朦朧としているがぎりぎり意識はある。話をするなら最後の機会になるだろう。だから来て欲しかったんだ。」
「解ったよ。それなら美穂と颯太も連れて行く。」
「そうしてくれ、じゃあな。」
マサ兄はそう言って電話を切った。
僕は会社に電話を入れ、事情を伝え休暇の申請をした。それから美穂と颯太にも準備ができたらホスピスまで来て欲しいと伝えた。幸い美穂の会社はまだ正月休み中で、颯太の学校も冬休みだった。僕は先に家を出てホスピスへと向かった。時間的には車を使うと渋滞に巻き込まれる恐れがあったため、電車で最寄り駅まで行きそこからはタクシーを使った。
ホスピスに着いて母の部屋に入ると、兄が母の枕元で何かを小声で話しかけていた。僕の姿を見ると
「母さん、シュンが来たよ。」
といって手招きした。
呼吸器をつけた母は、すっかり痩せこけており、以前のふっくらとしていた面影はなかった。年末にお見舞いに行ったときには、まだベットに腰掛けて話をするくらいの元気があったが、この数日間でまるで別人のようになっていた。枕元に行くと母は僕の方を見て何かを言いたそうな表情をしたが、声を出すのは辛そうな様子だった。
「母さん、シュンだよ。解るかい?」
僕が話しかけると母は突然、僕の手を握りしめ、掠れた息のような声でこう言った。
「感謝してます、感謝してます。もう、皆さんには感謝しかありません。」
僕は思わずマサ兄の方を見上げたが、マサ兄はただ首を振った。
「鎮痛用のモルヒネを投与しているから、もう誰が誰だか解っていないようだ。ただ話しかければ返事はある。話したい事があれば、今のうちに話しておけ。俺はちょっと看護師さんと話をしてくる。」
兄はそう言って病室を出て行った。僕はそれからただ心に浮かんだ言葉をひたすら母に話しかけた。
「ねぇ、母さん。僕は自分が【ひまわり】みたいに無邪気で明るい性格になれなかったのは、母さんのせいだと思ってずっと恨んでいた。まるで呪いをかけられたみたいにね。でもそれは間違いだって事に気がついた。きっとそれは僕自身の問題だったんだ。変われるきっかけはいくらでもあった。でもそれを拒絶していたのは、僕自身の生まれ持った気質みたいなものだったんだよ。でもね、矛盾しているようだけど、変わる必要なんて無かったんじゃないかって今は思えるようになったんだ。【あじさい】だろうが【アサガオ】だろうがそんな事は関係なく、そのままの自分を受け入れて周りの目なんか気にせずに生きていけば良かったんだよね。」

母にはおそらく僕の話が伝わっていないと思ったが、僕は構わずに喋り続けた。
「それから、新しい友達ができたんだ。彼は僕と同じような境遇で生まれ育ってきた。だから僕の抱えている孤独や葛藤を本当の意味で理解してくれている。僕は颯太が生まれてからは家族と一緒に仲睦まじく過ごせればそれで十分だと思っていた。だけど家族にだって話せない事ってあるだろ?だからこんなに心の通じ合った友達が出来て本当に嬉しかった。今の僕にはそういう存在が必要だって事に改めて気づいたんだ。彼の暮らしているのは南国の島でね、海があって豊かな自然に恵まれていて、ちっぽけな悩みなんか忘れてしまうような素晴らしいところなんだよ。僕もそんなところに生まれてたら、あるいは【ひまわり】みたいな人になれたんじゃないかなって思ったくらいだ。でも、残念ながら僕はそこに行くことは出来ない。だって、それはおとぎ話の世界なんだから。」
「感謝してます、感謝してます。もう、皆さんには感謝しかありません。」
それから母はまた同じ言葉を繰り返した。やはり、僕の言葉は母には届いていなかったようだが、それは今となってはどうでも良かった。
「母さん、今度来たときには皆さんに配れるように感謝状を持ってくるよ。」
僕は母の言葉に応えてそう言った。すると母は突然笑顔になり、瀕死状態とは思えないほど大声で笑い出したので、僕も思わず笑ってしまった。
「音楽でもかけようか?『この世の花』でいいよね?」
なんとなく母がこの曲を聞きたがっているような気がしたので、僕はテープレコーダーのスイッチをいれた。すると母はまるで指揮者のように両手を上げて、曲に合わせて小さく手を左右に振り始めた。目元からはいつの間にか一筋の涙がこぼれていた。
少しして兄が美穂と颯太を連れて、病室に戻ってきた。美穂は枕元に駆けつけ、母の手を握りしめ懸命に励ましの言葉をかけていた。颯太はどうしたらいいか分らない様子で母のことをただ呆然と見つめていた。それから兄が僕の耳元でぼそっと呟いた。
「最後に話はできたのか?」
「ああ、出来たよ。」
「どんな話をしたんだ?」
「【ひまわり】と【あじさい】の事。それから南国に暮らしている友達の話。」
「何だそれ?」
兄はそう言って首を傾げたが、その後、
「よく解らないけど、良かったな。」と言って僕の肩をポンと叩いた。
母が亡くなったのはそれから三日後の事だった。
母の葬儀は親族だけで密やかに行われた。僕の家族と兄、母の弟である叔父とその息子の従兄弟が参列した。美穂は棺の前でずっと泣きじゃくりながら手を合わせていた。颯太は人の死に立ち会うのは初めてだったせいか、初めはきょとんとした顔をしていたが、それでも冷たく人形のようになった母の亡骸をじっと見つめながら、突然、大粒の涙をポロポロと流し始めた。僕は涙を拭いてあげてから、颯太の事をきつく抱きしめた。
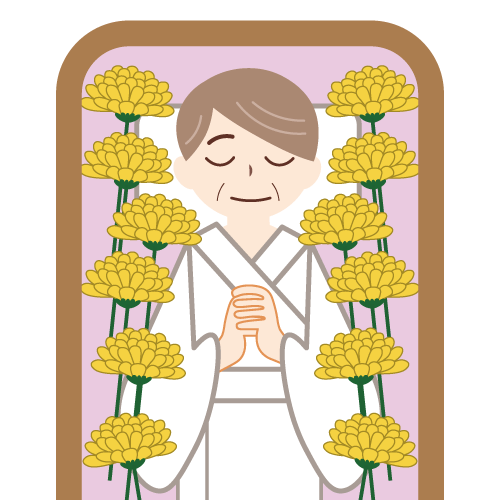
僕と兄は覚悟ができていたせいか、涙することはなく母の亡骸をただ無言で見つめていた。そして兄がどう感じていたかは解らないが、僕の中では母の死によってずっと抱え続けていた何かが厳かに終焉を向かえようとしていた。母によって占有されていた、あるいは母のために取ってあった僕の心の一部分は、その死とともぽっかりと穴が空いたが、心はその空白を埋めるようにトロトロと溶け始め、ゆっくりと形を変え始めていくのを感じた。
やがて母の49日もつつがなく終わり、以前と変わらない日常が戻って来た。季節はあっという間に過ぎ、ここ数年続いている暑すぎる夏がまたやってきた。僕はその日、残業がなく珍しく早い時間に帰宅していた。
「おかえりなさい。今日は早かったわね。」
美穂は例によって撮りためていたドラマの録画を見ていたが、すでに缶ビールを1本開けていた。
「ただいま。やっと仕事が落ち着いてきたんだ。これから少しは早く帰れそうだ。」
「それは良かったわね。ご飯にする?それとも先にお風呂にする?」
「汗だくだから、風呂に入ってからご飯にしようかな。」
「わかったわ。じゃあ、用意しておくわね。」
いつもの会話だったが、僕はその日、どうしても美穂に話したいことがあった。颯太は食事をすませて自分の部屋にいるようだったので、これは良い機会だなと思った。
「あのさ、久しぶりに一杯やらないか?」
僕がためらいがちにそう言うと美穂は少し、驚いたようだった。
「良いけど、珍しいわね。あなたから言い出すなんて。今日って何かの記念日だったかしら?」
「いや、そういう訳じゃないんだけど、その、去年の今頃に一緒に飲んだ時の事って覚えてるかな?君に頼まれて小説まがいの話をした事。」
「もちろん、覚えているわよ。王妃の物語でしょ?でもあれから色々あったじゃない。だからもうあんまり触れない方がいいかと思っていたんだけど。」
「実は、物語は完成していたんだよ。それで君にずっと聞いて欲しかったんだけど、なかなか機会が無くてね。できれば今日、続きを聞いてくれないかな?」
僕がそう言うと美穂は複雑な表情を浮べ、申し訳無さそうにこう言った。
「実は見られなかったドラマが溜まっているのよ。なかなか時間が無くて…。今はその続きが気になって仕方ないの。」
僕は落胆したが、今までの経緯からして仕方がないかと諦めた。
「そうなんだ…。それならまた次の機会にしよう。」
すると美穂はそんな僕の様子を見て、ニヤニヤと笑いながらこう言った。
「なーんてね、実は私もあの物語がどうなっていくのか気になっていたの。でも私からはなかなか言い出し辛くて…。解るでしょう?ずっとあなたから切り出してくれるのを待っていたの。でも、続きを聞く前に一つだけ聞いてもいい?」
「いいけど?どんな事かな?」
「最後はハッピーエンドで終わるのかしら?そうじゃなければ、悪いけど聞きたくないのよ。」
美穂は断固とした口調で僕に訴えた。
「それは大丈夫、最後はみんな幸せになる、保証するよ。」
「良かった。それなら続きを是非、聞きたいわ。あ、そういえば、お義母さんからいただいた美味しい日本酒がまだ残っているの。甘口端麗で口当たりが良くて、そんなに強いお酒じゃないから、あなたもきっと気に入るはずよ。キンキンに冷やしておくわね。」
美穂はそう言って、ドラマの再生を中断して、どこか楽しげに食事の準備を始めた。僕は急かされるように浴室へ入り、これから美穂に話す内容を整理した。そして王妃が復興した【お国】で、ぎこちない笑顔を浮べながらアリゼ達と再会を果たし、心地よい海風の吹く小高い丘の上で歓喜の涙を浮べている様を思い浮かべた。その王妃の姿は自然と亡くなった母の姿と重なり、僕の心を激しく震わせた。



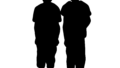
コメント