王妃がアリゼの島に行った後から、話は再開する。アリゼは島の近海に停泊していた謎の黒船から、石炭に代わる燃料として薪の調達を頼まれていた。不審な頼み事とは思いながらも薪を提供し、予想外の報酬を貰っていた。そして薪に不足があったため追加分として再度、調達する約束をしていた。そのためアリゼは森の中に行き、倒木を探し薪を拾い集めた。足りない分は斧で小枝を切り落とし補充した。
そして3日後に約束どおり、小型の帆船に薪と新鮮なフルーツを積み、黒船の停泊地へと向かった。
「おじさん、いるかい?約束通り、薪とフルーツを持ってきたよ。」
黒船の側までいくとアリゼは甲板に向かって叫んだ。すると、面識のある初老の紳士が待ち構えていたかのようにひょっこりと顔を出し、以前と同様によく響くオペラ歌手のような声で話しかけてきた。「おお、待ってたよ。よく来てくれた。また荷台を降ろすから薪を積み込んでくれるかな?」
アリゼは紳士の指示に頷き、薪とフルーツを荷台に載せ甲板まで上げる作業を数回繰り返した。全ての荷物を積み終えると、紳士からまた甲板まで上がってきて欲しいと誘われたが今回は迷い無く荷台に乗った。紳士は今日もスーツ姿で、白い手袋を差し伸べ出迎えてくれた。「ありがとう、本当に助かったよ、これでようやく母国に帰れる。それにあれから新鮮なフルーツの夢ばかり見ていたんだ。これで夢からも解放される。」
紳士はそう言って笑った。
「それはよかったね、おじさん。こちらこそ、薪ぐらいでこんなに沢山報酬を貰って申し訳ないくらいだ。おかげで暮らしもずいぶん楽になるよ。」
「ところで、まだ君の名前を聞いていなかったね。私はプロムスだ。」
「僕はアリゼっていうんだ。よろしく、プロムス。」
「アリゼか、良い名前だね。どういう意味があるんだい?」
「この国の言葉では『ひまわり』っていう意味があるらしい。船乗りで酒飲みの親父が名付け親なんだけど…でもそのいきさつまでは話さないよ。」
「ははは、そう警戒しなくていい。もう君の事を根掘り葉掘り聞こうなんて思っちゃいないさ。」
「逆に聞きたいんだけど、この船の持ち主は誰なんだい?おじさんの船なのかい?」
「うーん、こちらも君と同様に事情があってね、詳しい事は話せないんだ。でも我が国のさる高貴なお方の船とだけ言っておこう。私はその方の秘書をしている。」
「ふーん、これだけの船を所有しているんだから、相当なお金持ちだろうとは思ったけど、やっぱりね。さて、それじゃ僕はそろそろ帰るよ。またこの島に立ち寄る事があったら、力になるから呼んでくれよ。もっとも、こんな小さな島に用事なんてそうそうないだろうけどさ。」
「ありがとう、そうさせてもらうよ。ところでその…この船の主が君にどうしても直接お礼をしたいと言っているんだが、良かったら会ってもらえないかな?」「え、それは遠慮しておくよ。大した事はしていないし、それにこんなみすぼらしい格好で会うのもどうかなと思うし…。」
「そんなにかしこまらなくていいんだよ。気さくなお方だから気を遣う必要もない。でも、君が迷っているんなら、こうしないか?明日の夜、ディナーに招待したいんだがどうだろう?そうすれば身綺麗な格好に着替えてから来られるだろう?それとも、まだ私が信用できないかね?」「そういうわけじゃなんだけど、正直、あんまりそういう堅苦しい場には慣れてないんだ。」
「ふむ、無理にとは言わないが君も、島の監視員をやっているんならいずれは正式な社交の場に出る事もあるだろう。今のうちに慣れておいた方がいいんじゃないかな?」
プロムスのその言葉にアリゼの心は揺らいだ。確かにこれからそういう機会が増えてくるかも知れない。それにこんな最新の黒船の中に入れるなんて滅多にない事だ。迷ったが、結局はその申し出を受けることにした。「わかったよ、おじさん、じゃなくてプロムスだったね。ありがたく招待を受けさせてもらうよ。それで、明日はいつ頃くればいいかな?」
「そうだな、日没の少し前くらいに来てくれれば準備ができていると思う。君が迷わないように船の灯は全て点灯しておくよ。」
「日没前だね、解った。なるべく失礼の無い格好をしていくよ。」
「うんうん、待っているよ、アリゼ君。これはきっと、君にとって一生忘れられない経験になるはずだ。楽しみにしていてくれ。」
そう言ってプロムスが手を差し伸べてきたので、アリゼは戸惑いながら握手を交わした。
「それは、ちょっと大袈裟だね…。まぁいいけど。じゃあプロムス、また明日。」
「ああ、気をつけて帰ってくれ、アリゼ君。」
それからアリゼは新たな報酬を受け取り、島へと帰っていった。
翌朝、王妃はディナーの準備に余念がなかった。使用人達には事細かく指示を出し、調理室に出入りしメニューのチェックまでしていた。使用人達は王妃に声をかけられるたびに動揺し細かなミスを繰り返したので、黒船の中にはただならぬ緊張感が漂っていた。見かねたプロムスは慌てて王妃をなだめた。「奥様、そのように細かい指示ばかり出されていては作業が一向に進みません。この船の使用人達は選りすぐりの者ばかりです。お気持ちは解りますが、お任せした方がよろしいかと。」
「そ、そうよねぇ。解ってはいるんだけど、何かしないではいられないの。ところでプロムス、私の今日の服装や髪型はどうかしら?最近、あまり身だしなみを気にしたことがなかったから、意見を聞きたいの。」
プロムスは長年、王妃に仕えていたが、これほど落ち着きの無い王妃を見た事がなかったので、その姿が可笑しくもあり奥ゆかしくも感じられた。
「奥様は、とてもお綺麗です。そのドレスも髪型も髪飾りもとても似合っております。私のような年寄りから言われてもどうかと存じますが、とても魅力的です。」
「それは若い頃の話よね?私もずいぶん年を取ってしまったし、以前のように派手なドレスも似合わなくなっているんじゃなくて?あの子が、ヒースが母様がこんなオバさんになっちゃったって、がっかりしなければいいんだけど…。」
王妃は鏡台の前に座り、ため息をつきながらしきりに自分の容姿を気にしていた。「いいえ、決してそんな事はありません。私は長い間、奥様に仕えておりますが、その魅力は幾分も損なわれてはおりません。もっとご自分に自信を持ってください。」
実際に王妃は実年齢よりもずっと若く見えた。またプロムスはお世辞ではなく、王妃の事を生まれつき備わった天真爛漫さに加えて、大人の成熟した魅力を兼ね備えた女性だと感じていた。そして王宮のほとんどの人間が、激しい気性と過去の行動から王妃のことをただの傲慢な女性としか見ておらず、その本質が理解されていないことが残念でならなかった。
「大丈夫です、奥様。準備が抜かりなくできているかは私がチェック致しますので、それまではどうかお部屋でゆっくりしていてください。」
プロムスにそう言われて、王妃はようやく、少し落ち着きを取り戻した。
「わかったわ、プロムス。よろしく頼むわ。」
王妃がそう言うと、プロムスはニッコリと微笑んで部屋を出て行った。「果たして私は、あの子に受け入れてもらえるのだろうか?いや、もうなるようにしかならないわね。」
王妃は深くため息をつき、もう二度と会えないと思っていた我が子に再会できるかもしれないという期待と不安を抱えながら夜が更けるを待った。その頃、アリゼはディナーに行くための服を選ぶのに余念が無かった。王宮から着てきた服はすでに小さすぎて着られなくなっていたので、正式な場に着ていく服を持っていなかったからだ。村にある数少ない店を回ってみたのだが、何を選んだらいいかわからず途方に暮れていた。そこでやむを得ずルイカに事情を話して相談しようと思い、家に帰るとその矢先に、ルイカが息を切らせてアリゼの元にやってきた。
「ルイカ、ちょうど良かった。相談したいことがあったんだ。この村の正装ってどんなものかな?実はディナーに招待されているんだけど、着ていく服が無いんだ。」
アリゼはルイカに戸惑いながらそう告げたが、ルイカは今にも泣き出しそうな顔をして、全く聞く耳を持たなかった。
「アリゼ、一体何処に行っていたの?ずいぶん探したのよ。何の事か解らないけど、すぐに来て。ネネが、お婆ちゃんが…。」
ルイカのその一言でアリゼは全て理解した。最近、バハリの母親のネネの具合が思わしくないと知っていたからだ。容態が急変した、そう感じた。「ルイカ、解った。すぐ行く。」
それからアリゼとルイカはネネのいる部屋に駆けつけた。その時にはネネはすでに呼吸が荒く、意識が遠のきひどく衰弱しているように見えた。枕元に座っていたバハリは、アリゼが来たのを見るとネネの耳元に顔を寄せ話しかけた。「母さん、アリゼが帰って来たよ。解るかい?」
ネネはその言葉に反応し目を細めて、アリゼの方をゆっくりと見上げた。
「ああ、アリゼかい。もっと側に来て顔をよく見せておくれ。」
「ネネ、気をしっかり持って。大丈夫だから。」
アリゼはネネの枕元に座り、すっかり痩せ細り冷たくなった手をしっかりと握りしめた。
「アリゼ、ごめんね、子供の頃はお前の面倒をあんまり見てあげられなくて。私も異人さんのお世話なんてしたことがなかったから、初めはどう接したらいいか解らなかったんだよ。」
「そんな事、全然気にしてないよ。それにいきなり異人の子がきたら誰だって戸惑うよ。それでもネネはそんな僕のことを本当の子供のように可愛がってくれたじゃないか。村の子に苛められた時は慰めてくれたし、イタズラをした時にはきちんと叱ってくれた。僕にとっては母様も同然だったよ。」「有り難いことを言ってくれるね。それとルイカ、あんたには一番苦労をかけたね。私も年を取っていたから家の事がどうしても一人ではできなくて、手伝ってもらうしかなかったんだ。お友達とも遊びたい盛りだったろうに、それをご飯の支度やらお掃除やら手伝わせて…」
「ううん、ネネ、私も初めのうちはお料理やお洗濯がうまくできなくて、落ち込んだしお友達と遊べなくて辛かったけど、だんだん家事に慣れてくると自分が少しずつでも成長しているんだなって思えるようになって嬉しかった。それにネネがいてバハリがいて、アリゼがいて、家族で一緒に過ごせるだけで私は充分幸せだったわ。だからネネ、もう少し私達の側にいて。」
ルイカがそういうとネネは顔をしかめてうっすらと笑顔を浮べた。
「ルイカ、お前は本当に優しく賢い子に育ってくれたね。これで死んでしまったお前の母様にも顔向けができそうだよ。バハリ、ルイカとアリゼの事を頼んだよ。それから、あんまりお酒は飲み過ぎないこと。ルイカに迷惑をかけるからね。」
「解ってるよ、母さん。出来の悪い息子で迷惑をかけたね。でもさ、俺はこういう風にしか生きられないんだ。そういう不器用な男に育てたのは母さんだぜ。」
「ふふ、そうだねぇ。育て方を間違ったかねぇ。でもあんたはだらしないところもあるけど、父さんみたいな立派な海の男になった。それと普段は強がってるけど、実はとても優しくて涙もろくて…。そういうところも父さんにそっくりだ。」「なあ、母さん、ルイカとアリゼはずいぶん大人になった。ただ俺が言うのもなんだけどまだまだ、経験が足りなくて危なっかしいところがある。でもこれからは俺が二人を見守っていくから安心してくれ。」
バハリのその言葉を聞いてネネは口元には微かな安堵の笑みを浮かべ満足をしたように息を引き取った。目元からは微かな一筋の涙がこぼれた。覚悟を決めていたバハリは、冷静にその死を受け止めることができたが、アリゼとルイカはその場で泣き崩れた。
大切な家族の死に直面してアリゼは悲嘆にくれた。死は誰にでも訪れるもの、頭では理解していたが、その悲しみは想像以上の痛みと喪失感をアリゼに与えた。自分の心の奥底に大切にしまってあった物が、ネネの死によって一瞬にして失われてしまったような気がした。アリゼは堪えきえれず、ひとり外に飛び出し海岸線まで走った。そこでは豊かな恩恵を与えてくれる太陽が今にも海に没しようとしていた。見慣れているはずの風景が、いつになく尊いものに感じられた。アリゼは息を切らしたまま砂浜に座り、その様を眺めた。これからネネを家族で見送らなければならない、早く家に帰らねばと思いながらもアリゼはその場から一歩も動けずに蹲っていた。






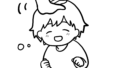

コメント