時間はすでに17時を過ぎていたが、母と妻の美穂の話は尽きる事がなかった。僕からすれば、どうでもいい話を延々と続けている。颯汰はお菓子をたくさん食べて、お小遣いも貰って初めのうちはご機嫌だったがいい加減、退屈してきたようだった。僕は早く家に帰りたくて仕方がなかったので折りをみて母に帰ることを告げた。
「シュン君、もう帰っちゃうのかい?まだいいじゃない。晩ご飯を食べて行きなさいよ。」
「いや、悪いけど明日から仕事だから。連休明けは仕事が溜まってて忙しいから少しは早めに休んでおきたいんだ。」
「…そうかい、じゃあ仕方ないわね。美穂さんも颯ちゃんもまた婆ばに会いに来てね。」
母はそう言って、颯太の手を握りしめた。
「うん、また会いに来るよ、お婆ちゃんも体に気をつけて元気でいてね。」
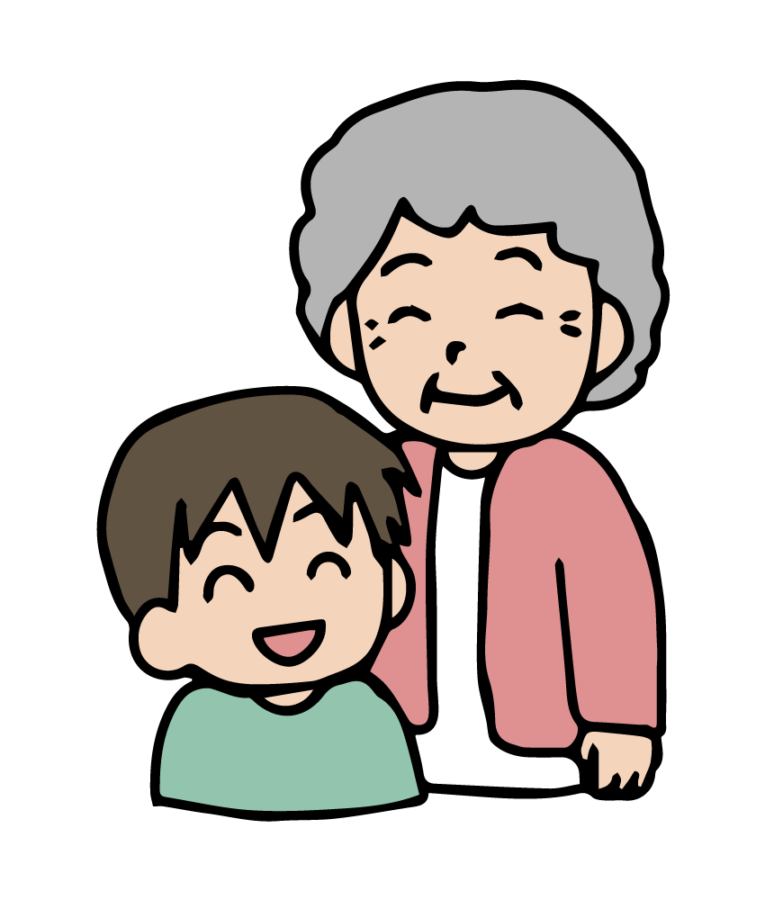
「ありがとうね、颯ちゃんは本当に優しい子だね。温かくてほんとにお手々もすべすべだ。だんだん、シュンの小さい頃に似てきたね。」
母は少し涙ぐみながらそう言ったが、僕はそれを聞いてうんざりしていた。
「じゃあ、帰ろうか、美穂。」
僕がそう切り出すと美穂は少し戸惑いながら母に話しかけた。
「そうね。お義母さん、これから寒くなってくるからお体に気をつけて下さいね。」
「ありがとう。美穂さんはいつまでも若々しいわね、羨ましいわ。シュンは相変わらず少しボーとしているところがあるから、しっかり者の美穂さんが側にいてくれて助かるわ。」
「いえいえ、お義母さんこそ、いつも感覚が若々しくて素敵だと思いますよ。」
美穂と母の話が長くなりそうだったので僕は苛立ち、遮るように会話に割り込んだ。
「美穂、道が混み出す前に帰ろう。スーパーで買い物もしなきゃならないんだろ?」
「え、わかったわよ。じゃあ、お義母さんお元気で。」
「お婆ちゃん、またね。」
颯太がそう言って手を振ると、母は名残惜しそうに階段を降りて玄関まで出迎えようとしたので、僕は慌てて引き留めた。
「母さんは膝が悪いんだから、ここでいいよ。また来るから。明日はマサ兄が来るんだよね。よろしく言っておいてね。それじゃ。」
早口でそう言って見送りを拒むと、母は少し寂しそうに微笑んだが、結局は2階のリビングから降りてくることはなかった。
それからハッチバックのコンパクトカーに美穂と颯太を乗せ、帰路についた。母の住む家までは、車だと1時間程度の距離だったが、助手席に乗った美穂はなんとなくご機嫌斜めな様子で無言だった。後部座席にいた颯太もその雰囲気を感じ取ったのか、何も喋らずにただ外の景色を眺めていた。
埼玉県の郊外にある母の家に行ったのは9月下旬の3連休の最終日だった。
再婚した義父が昨年、他界してから母は一人で暮らしていたが、一人になってからは急に抜け殻のようになってしまい、家事もほとんど手に着かない状態だった。そのため部屋は常に埃っぽく、流しにはいつも食器や生ゴミが山積みになっていた。
週に3日程度ヘルパーさんとケアマネージャーが様子を見るために訪問し、残りの日は兄が定期的に訪問して面倒を見ていた。施設に入ることを幾度となくすすめたみたが、いつものらりくらりとかわされ、母は頑として首を縦に振らなかった。僕は時折、兄が行けない日に頼まれて様子を見に行っていた。なんとなく美穂と颯太を連れて行くのは嫌だったので、いつも一人で行くようにしていたのだが、その日は美穂に押し切られ颯太を連れて3人で行くことになった。
家に着くと僕と美穂は分担して家事をおこなった。僕は掃除機をかけ、床をモップで水拭きした。美穂は食器を洗いシンクの掃除をして、ドロドロになっていた生ゴミをまとめた。電気ポットに残っていたお湯は捨てて中を綺麗に洗い、水を入れ替えてお茶を入れた。その間、颯汰にはお菓子を食べさせて、母の相手をしてもらっていた。
母は「お掃除なんてしなくていいわよー。」と気楽に笑っていたが、何しろ埃っぽさに我慢ができなかったので僕と美穂は母の言葉に微笑んで頷きながら、黙々と作業をしていた。掃除を始めてみると意外にやることが多くて、仕上げにトイレ掃除まで終え一息着いた頃には、すでにお昼時を過ぎていた。それから美穂は早起きして作ったおかずとおにぎりをタッパーから出して、洗った皿に移しかえレンジで温めた。それを食卓に並べ、ようやく昼食をとれた。
帰りの車の中で、僕は美穂の機嫌が悪い理由はなんとなく解っていたが、あえて聞こうとは思わなかった。僕にとっては生理的な問題だったので、理解してもらうことは難しいと思ったからだ。美穂も半ば諦めてはいるのだが、それでも感情的には釈然としなかったのだろう。

僕は気まずい沈黙に耐えかねて、なんとか雰囲気を変えようと話題を切り出した。
「今日は二人ともお疲れ様。本当に助かったよ。帰りに何か美味しいものでも食べて帰ろうか?といってもファミレスか回転寿司かどっちかになっちゃうけどね。」
僕は努めて明るく言ったつもりだったが、美穂はあっさりと僕の言葉を無視した。
「今日の晩ご飯はお惣菜でいいわ。他の買い物もあるからいつものスーパーに寄ってくれない?」
僕は軽いため息をついて頷き、スーパーの駐車場に車を停めた。
それから美穂はいつものようにテキパキとお惣菜と明日のお弁当のおかずを品定めして買い物を済ませた。僕と颯太はただその様子をぼんやりと眺めながら、買い物かごを乗せた台車を無言で押していた。

それでも家に帰ってお惣菜を食べてビールを飲んでいるうちに、美穂も気持ちがほぐれたせいか、いつもの調子に戻っていた。颯太もそれに合わせて、少しずつ笑顔をみせるようになっていた。
「お義母さんの話はいつ聞いても面白いわ。切り口が独特で話が軽快なのよね。たまにドキッとするような毒舌もあるけど。やっぱり色々な経験をなさっているからかしらね~。」
「そうだね、お婆ちゃんの話って面白いよ。笑っちゃう。」
美穂に合わせて颯太もそう言った。
美穂は母の事をとても気に入っているようだった。そのせいか母の家に行くと母と美穂がほとんど話をしており、僕と颯太はただの聞き役になっていることが多かった。端から見たら僕が婿養子で美穂が実の娘のように見えたかも知れない。
僕としては、きっと母は他人の目からはそういう人に見えるんだろうなと達観していたが、これ以上美穂の機嫌を損ねたくはなかったので、何も言わずにただ笑って頷いていた。
いつもの食卓の雰囲気がようやく戻って安心したが、母に会った事と久しぶりに運転をしてたせいか、どっと疲れが出てきた。そのため食器洗いを買って出て、早めにお風呂に入り休ませてもらうことにした。美穂はまだ何かモヤモヤしたものが残っているせいなのか、撮りだめていた連続ドラマを見てから寝ると言っていた。
久しぶりに母に会った事も影響していたのかも知れないがその夜、僕は久しぶりにやんちゃな王子の夢を見た。それはアリゼが島の監視員の仕事に就いて兄との再開を果たした後の物語だった。
#失われた王国


コメント