美穂に王妃の物語を話してから、僕は自分が何故、それを書こうとしていたのか考え込むようになっていた。そして悩んだ末、この物語についてはしばらくの間、凍結することにした。美穂もそんな僕の様子を感じ取ったのか、あれから物語の続きを聞きたいとは言い出さなかった。そのため、何事も無かったかのようにいつもの日常が過ぎていった。
美穂の言うように僕はこの物語の結末、つまり答えを持っていた。でもそれは漠然とした感情のパラドックスであり、素数のように割り切れないものだった。僕はそれを数学の手法で言えば帰納法や演繹法を使うようにフィクションの世界に書くことで証明しようとしていた。それが、あの日美穂に言えなかった事だと気づいたが、言葉で説明するのはとても難しかったし、理解もしてもらえないだろうと思ったので改めて説明する気にはなれなかった。心理学的な視点で見れば箱庭療法に近いのだろうが、果たして今、やるべき必要があることなのかと疑問に感じたし、そこに貴重な時間と労力を割く事には意味を見いだせなかったからだ。
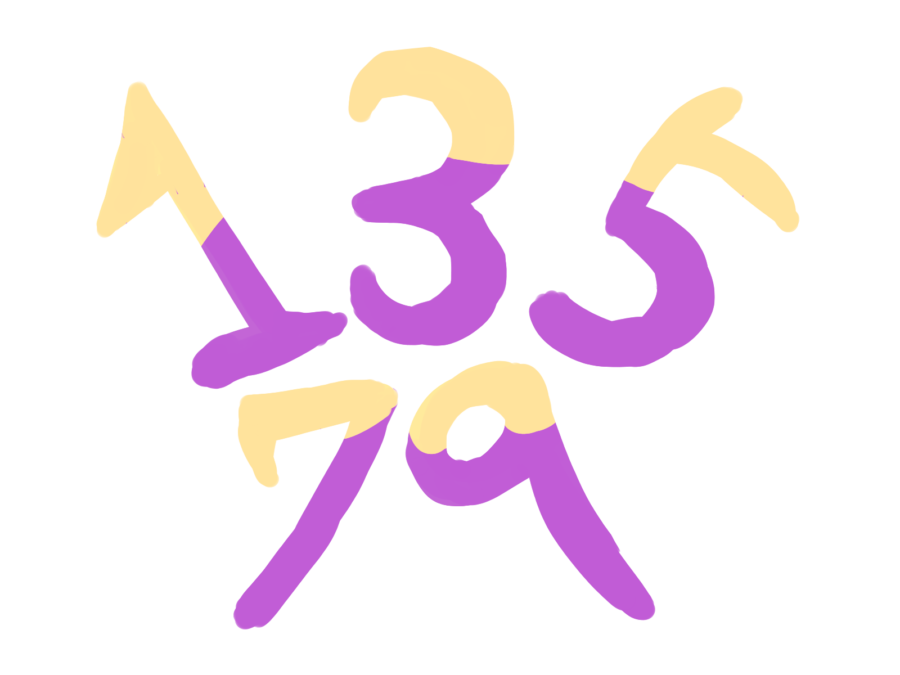

その時間に颯太とゲームをして遊んであげることもできるし、家族で旅行に行く計画も立てられるだろう。美穂と持ち家の購入を検討する時間にも充てられるし、僕自身もリスキングをして資格を取ったり、将来を見据えてNISAを運用することも可能だ。そして何よりも今は、家族と過ごす時間こそ大事にすべきではないかと考えるようになっていたが、その矢先にあの不可思議な出来事は起こった。
その日僕は、研修のため市ヶ谷にある本社オフィスを訪れていた。研修内容はマーケティングや経営戦略、企業組織論などで、中堅社員向けに数ヶ月に1回、定期的に行われていたものだった。午前中は座学、午後はいくつかのチームに分かれてディスカッションと発表を行った。座学は専門用語ばかり覚えさせられ、ディスカッションはコミュニケーションを深めるという理由で、初めて会う社員同士でチームを組ませられたので気を遣ってしまい、終わる頃にはいつもぐったりしていた。ただ定時にはきっちりと終わりにしてくれたので、拘束時間の短かい事が救いだった。
研修後に毎回、参加者で軽い飲み会があり一応顔は出したが、乾杯の挨拶が終わると早々に帰ることにした。引き留められはしたが、今日は妻が仕事で帰りが遅く、子供を一人で放っておけないのでと言って丁重に断った。もちろん、それはだらだらと飲み会にはいたくない口実だったが。
それから僕は靖国通りを市ヶ谷の駅へ向かって歩いた。まだ宵の口だったが11月に入り、日没が早くなったせいか辺りはすっかり暗くなっていた。コロナ渦が落ち着いた都心のオフィス街は飲み会に繰り出すビジネスマンやOL達で賑わっていたが、対照的に春には見事な景観を見せていた桜並木は、すっかり落葉して冬眠状態に入ろうとしていた。
足早に駅に向かっていたが、駅前にある旅行代理店のウィンドウを見てふと足が止まった。そこにはハワイのカウアイ島にある大判の広告が貼ってあり、見事なパームツリーが数本そびえ立っていた。ふと王子の物語に出てくるシュロの木が頭に浮かび、こんな感じだったかなと思い、つい魅入ってしまった。すっかり遠ざかっていた常夏の風景に懐かしさを覚えた。
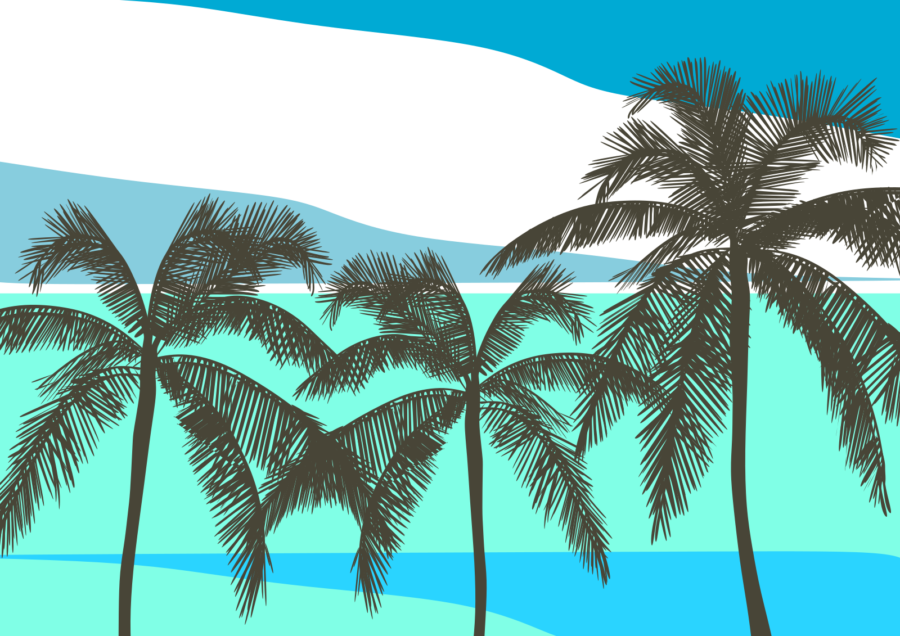
ウィンドウには僕の姿もうっすらと映っていた。くたびれた顔をしていて、確かに美穂の言うように何かの悩みを抱えている男のように見えなくもなかった。でも逆に何の悩みも抱えていない中年期の男がいるのだろうか?むしろ少数派じゃないのかな?そう思い苦笑しながら改めてウィンドウを見て、僕は自分の目を疑った。
そこには子供の頃の僕が映っていた。年齢的には颯太と同じ7,8才くらいだろうか、季節外れの半袖のTシャツと短パン姿で、読売ジャイアンツの野球帽を被りなんとなく不安げな表情を浮かべていた。僕は試しに右手を上げてみると、少年も右手を上げた。口角を広げ笑顔を作ってみると、少年もおなじようにぎこちなく笑った。僕は自分の頭がおかしくなってしまったのかと思い、目を擦り瞬きを何度も繰り返した。
それから改めてウィンドウを見直すとそこには、王子の服を着たアリゼが少年の僕の隣に立っていた。アリゼは少年の肩に手を置いてニッコリと笑いかけ、耳元で何かを囁いていた。すると少年は軽く頷きアリゼとともにパームツリーのある方へ駆け出し、あっという間にその姿を消した。

その後のウインドウには、少年やアリゼはおろか今の僕の姿すら映っていなかった。僕はパームツリーの広告に手を伸ばし、触ってみたがそれは何の変哲も無い硬質ガラスとありふれたポスターだった。それでも触っているうちに、硬質ガラスはジェル状の液体のようになり、中まで入っていけそうな感覚があった。少し迷ったが思い切って体重をかけて身を委ねてみると、僕の体はあっという間にジェル状の液体に包まれた。柔らかい泥の中に沈んでいく時のように、どこからが自分の体でそうではないのか解らなくなるような奇妙な感覚に襲われた。呼吸は普通にできていたので苦しくは無かったが、どうにも落ち着かなかった。どうにかして前に進もうともがいていると、突然、目を開けていられないほどの強烈な日差しが僕を待ち受けていた。
日差しを手で遮って辺りを見回すと、ムッとするような熱帯の湿気の多い海風が潮の香りを運んできた。目の前には海岸があり、物語に出てきた島で一番大きなシュロの木が悠々とそびえ立っていた。その下では数人の若者達が御座を広げ、酒と食べ物を片手に楽しそうに語らっていたが、僕の姿をみると一斉に驚きの表情を浮かべ喚声を上げた。
「シュン、君が本当にここに来られるとは思っていなかった。会えてとっても嬉しいよ!」
一人の青年が僕に話しかけてきた。それはすでに大人になっていたアリゼだった。
「シュン、会えて嬉しいわ。でも私達の事、忘れてたでしょ?ひどいわね。まぁ大人って色々考える事があるから仕方ないのかなぁ。でもここに来てくれたから多めに見てあげる。ふふ。」
隣に座っていた若い女性が僕をからかうように微笑んでそう言った。ルイカだった。
「シュン、よく来てくれたね。でも君は最近疲れが溜まっているんじゃ無いか?きっとここならリフレッシュできるよ。」
ドレッドヘアーをなびかせた青年、タフラがそう言った。
俄には信じられなかったが、僕は自分が作った物語の世界に入り込んでしまったようだった。おそらく夢の中ではない。南国の日差しと海風と潮の香り、波の音、風に揺れるパームツリー、これはリアルなものだ。ましてや僕はついさっきまで、会社の研修を終えて市ヶ谷の駅前にいた。ベッドの中にいたわけではない。
「シュン、急に呼び出して悪かったね。でも君とは一度ゆっくり話をしてみたかったんだ。」
アリゼがそう言ったが、僕はその前にどうしても確かめたい事があった。
「アリゼ、ここは現実の世界じゃない、でも夢の中でもない、そうだね?」
「その通りだ、シュン。ここは現実の世界じゃないし夢の中でもない。」
「じゃあ、一体、ここは何処なんだ?なぜ僕はここにいるんだ?」
アリゼは呆然としている僕を見て、ちょっと困ったように頭をかきながらこう言った。
「君達の生きている世界ではないけど、僕達にとってはリアルな世界なんだ。ただこの世界について説明するのはとても難しいんだよ。君だって現実世界で起きていることを、全部理論的に説明できるわけじゃないだろ?」
「なぁ、僕は急に心臓発作か何かを起して死んでしまったんじゃないのか?」
僕がそう言うとアリゼは突然、ぷっと吹き出して笑い出したので、僕は不快になった。
「笑い事じゃない、真面目に聞いているんだ。何が起きているのかきちんと説明してくれないか。」
「いや、ついつい笑っちゃったな、申し訳ない。でもさっきも言ったように説明が難しいんだよ。あえて言うなら、ありふれた言葉になっちゃうけど、どこでもない時空の狭間のようなものと考えてもらっていい。それに君は死んでいないし、戻ろうと思えばいつでも元の世界に戻れるから心配しなくていい。ここにいる限りは安全だ。だって当然だろ?ここは君が作った世界なんだから。」
僕はなんとか冷静になろうと、iPhoneを取り出した。時間と位置情報を確認しようとしたが、液晶は真っ暗で何も表示されていなかった。僕がまだ状況を理解できずに黙っていると、アリゼは続けざまにこう言った。
「シュン、君はいつだって頭で物を考えすぎる。僕だってまさか君がこの世界に来られるとは思ってもいなかったから、相当驚いているんだぜ。でも実際に君はここにいる。それでいいじゃないか。この奇跡の瞬間を大事にしよう。まずは乾杯しないか?」
アリゼがそういうとルイカとタフラも微笑んで頷いた。なるようにしかならない、僕はそう思い諦めてアリゼ達の待つシュロの木の下へと歩いて行った。
#失われた王国



コメント