存在平面の校舎には、奇妙な静けさがあった。
授業が終わったあとも、廊下や中庭にはほとんど人の気配がない。
それは、生徒たちが皆無口だからではない。
おそらく、誰もここで「会話をしよう」と思っていないからだ。
高志は、昼休みの時間に中庭へ出た。
中庭と言っても、そこには芝生も木陰もない。
ただ白く平坦な空間が、どこまでも広がっている。
校舎の外に出た先に、ぽつんとベンチが一つ置かれていた。
そのベンチに、ひとりの男が座っていた。
痩せた体つきに、くたびれたシャツ。
男は膝の上で手を組み、まるで自分の存在を隠すように、小さくうつむいている。
近づくと、男が気づいたように顔を上げた。
「……君も、観測科目の生徒?」
声はかすれていたが、どこか柔らかい響きがあった。
高志はベンチの端に腰を下ろし、無言でうなずいた。
「ここは、不思議な場所だよな。
気づいたら、誰かがいて、気づいたら、誰かがいなくなる。」
男は、空でも見上げるように、視線を上げた。
けれど、この世界には空も雲もない。
あるのは、どこまでも続く白い余白だけ。
「俺は、息子を残してきた。まだ三歳だった。」
ぽつりと、男が言った。
「最初は、どうしても戻りたかった。
でもさ、この場所にいるうちに、少しずつ思うようになったんだ。
“本当に戻ることが、あいつのためになるのか?”って。」
高志は、何も言えずにその横顔を見つめていた。
男の言葉は、自分の心にぴたりと重なっていた。
沙梨に教えられた紬の姿。
あの、どこか孤独なまなざし。
あの子のために、自分は何ができるのだろうか。
「……俺は、もう決めたよ」
男は、最後にそう言って立ち上がった。
その背中が、白い余白の中に吸い込まれるように、ゆっくりと遠ざかっていく。
「ねえ、高志さん」
いつの間にか、沙梨が後ろに立っていた。
「何考えてるの?」
高志は、すぐに答えられなかった。
ただひとつ、思ったことは。
この場所では、誰もが“戻る”ことだけが正解じゃないということ。
そして、自分はまだ、その答えを持っていないということだった。
それは、ほんの小さな違和感だった。
いつものように教室で「未練心理学」の授業を受けている最中、高志はふと、ペンを持つ手を止めた。
黒板には「人は未練によって縛られる」と、いつものように無機質な字で書かれている。
その下に、「未練の強さは現世への執着の度合いと反比例する」と、まるで数学の公式のような言葉が続いていた。
だが、その言葉が、この日の高志にはどこか白々しく思えた。
未練は、そんなに単純なものなのか?
誰かを想う気持ちや、過去に縛られる痛みを、数字や言葉で割り切れるものなのか?
授業の終わりに、校長のキドがひとこと言った。
「未練がある者ほど、戻ることに執着する。だが、それが本当に幸せかどうかは、誰にもわからない。」
その夜、存在平面の寮の部屋で、高志はひとり、紬の姿を観測した。
布団にくるまり、スマホの画面だけがぼんやりと明るい部屋。
紬は、何かの動画を眺めながら、微かに眉をひそめていた。
その表情に、高志は自分の記憶の中の彼女を重ねた。
幼い頃、眠る前に絵本を読んでやったとき、物語の続きをもっと聞きたいのに我慢していた顔。
母親に叱られて泣いたあと、こっそりと自分の腕にすがってきた夜。
けれど、目の前の彼女は、もうその頃の紬ではない。
自分のことなど、記憶の片隅にも残っていないかもしれない。
翌日、授業の前に、沙梨が隣の席で小声で言った。
「昨日、ちょっと変な顔してたよ。
まるでこの世の終わりみたいな顔をしてた。」
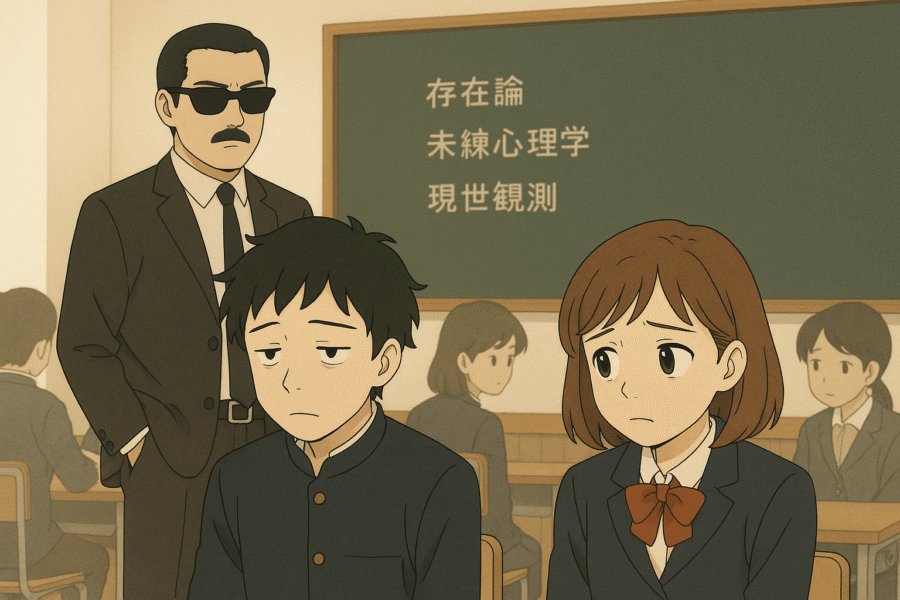
高志は苦笑した。
「そもそも、俺達もう死んでるじゃん…。
それにしてもお前は、俺の事をよく見てるな。」
「うん。私、あんたのこと、心配で何だかほっとけないんだな。母性本能ってやつ?」
沙梨は、まるでからかうように微笑んだ。
だがその瞳は、どこか本気だった。
授業の終わり、キド校長が告げた。
「来週から、境界実験を開始する」
その言葉が、教室の空気を少しだけ震わせた。
実験とは何なのか。
自分がここで、何を試されているのか。
そして、自分が本当に“戻りたい”のかどうか。
そのすべてが、高志の中で、静かにほころび始めていた。
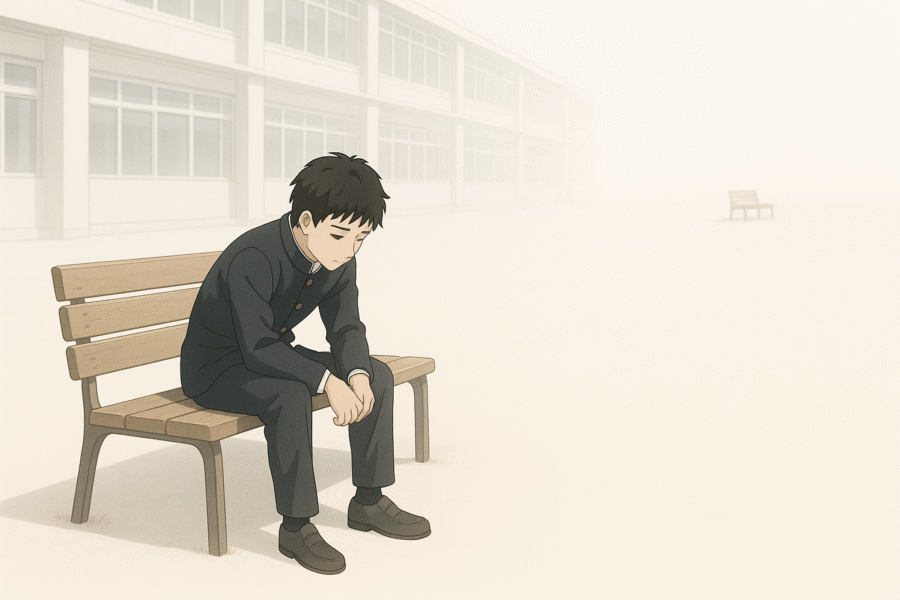
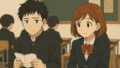
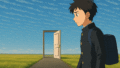
コメント