その日は、授業がすべて終わったあとだった。
存在論、未練心理学、現世観測──
どれも高志には、ただ言葉を追うだけで精一杯だった。
講義の合間、教室の空気がふっとゆるんだとき、
忘れていた感覚が、指先に蘇った。
ノートを閉じた瞬間だった。
──靴紐のざらりとした手触り。
──冷たく乾いた地面の感触。
──朝露に湿った空気の匂い。
何の変哲もない、ありふれた朝だった。
ほんの少しだけ早起きして、
ほんの少しだけ、早く家を出ただけだった。
駅へ向かう道も、すれ違う人の顔も、
見慣れた風景の中に、何ひとつ引っかかりはなかった。
角を曲がったとき、足元に目を落とした。
靴紐がほどけているのに気づいた。
しゃがみ込んで、何気なく結び直す。
きゅっと紐を引き締めた、その瞬間だった。
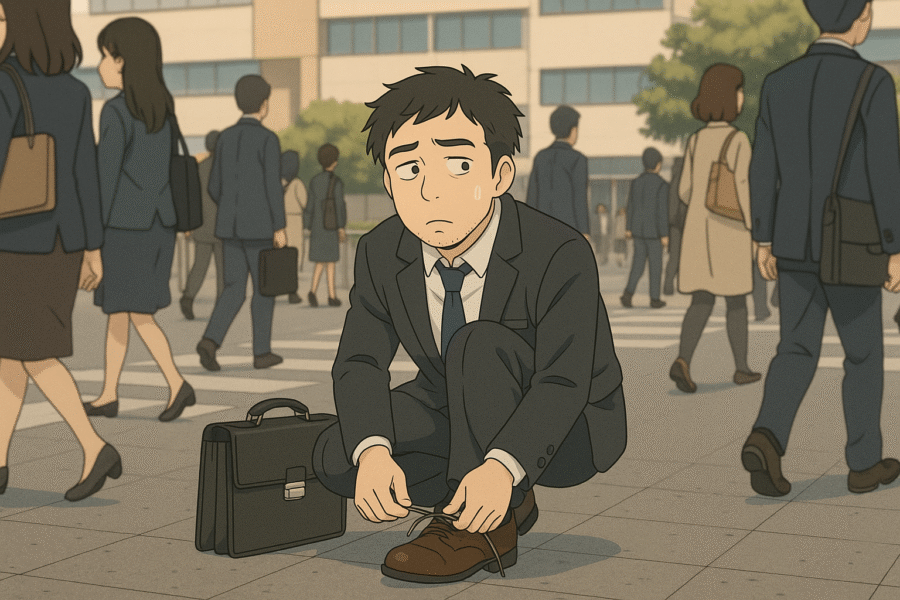
胸の奥に、重たい鈍痛が走った。
呼吸が詰まり、世界がにじんだ。
──ああ、まずい。
そんなふうに思った。
誰か、誰でもいい、手を貸してほしいと、心のどこかで願った。
けれど、声は出なかった。
体も、動かなかった。
世界は、すっと白く溶けていった。
最後に見えたのは、
自分の指先で、途中まで結びかけた靴紐だった。
輪ができかけたまま、途中で止まった結び目。
何かをつなごうとして、でもつなぎきれなかった、その形だけが、
ぼんやりと目に焼き付いていた。
そして、それも、すぐに滲んで消えた。
教室の隅、ノートを整理していた高志は、
遠い朝の手触りを思い出しながら、
ただ静かに、机の上を見つめていた。
隣では、沙梨がペンをくるくると回しながら、ノートの端に小さな犬の絵を描いていた。
彼女は、何かに気づいたように、高志をちらりと見て、
ぽつりと呟いた。
「……人生って、気づいたときには、もう次に行っちゃってるんだよ。」
高志は、答えなかった。
ただ、自分の手のひらを見つめた。
そこにはもう、靴紐も、アスファルトも、
朝の匂いも、何もなかった。
あるのは、白く空っぽな存在の平面だけだった。
それでも、高志は、
あの日の朝、自分が確かにそこにいたことだけは、
どうしても、忘れることができなかった。
──ただ、それだけだった。
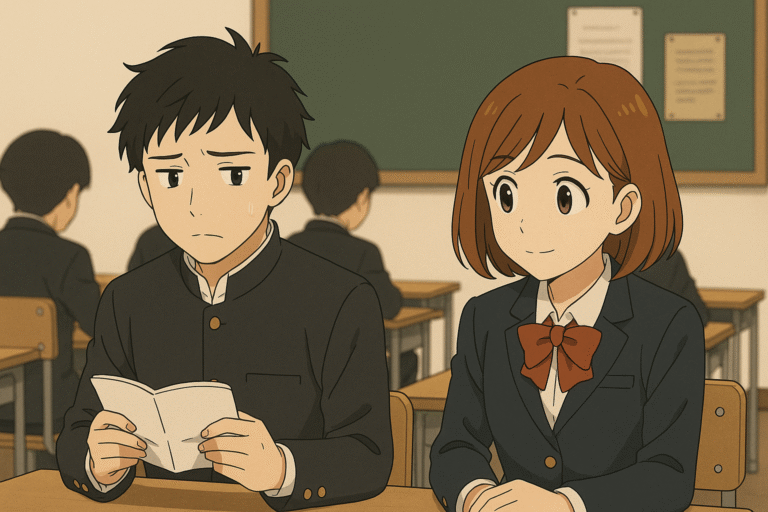

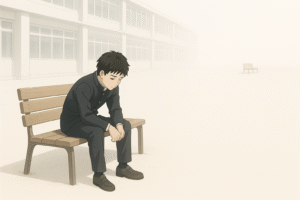
コメント