・2015年 秋
解雇通知を受けた日の夜、僕がまだ大学に通っていた頃の夢を見た。かれこれ15年も前の事になる。
僕は授業をサボって屋上でiPhoneで音楽を聴きながら煙草を吸っていた。仰向けに寝そべって吸いながら煙を吐くと、青空と煙が重なってとても青っぽく見えた。確か有名なロックバンドの曲でそっくりなシーンがあったよなと、バンド名を一生懸命思い出そうとしていた時、ガチャガチャと音がして屋上の扉が開き、いつものようにサキがやってきた。
「ラクダ、またサボって寝てるの?ほんとにぐーたらね、ぐーたラクダだ。」
サキは僕の事を勝手に「ラクダ」と呼んでいた。僕がラクダのイラストが描かれたパッケージの「CAMEL」という銘柄の煙草をいつも吸っていたからだ。それによく薄い茶色のパステルカラーの長袖Tシャツを着て、カーキ色の薄手のモッズコートを羽織っていたこともイメージが重なったようだった。
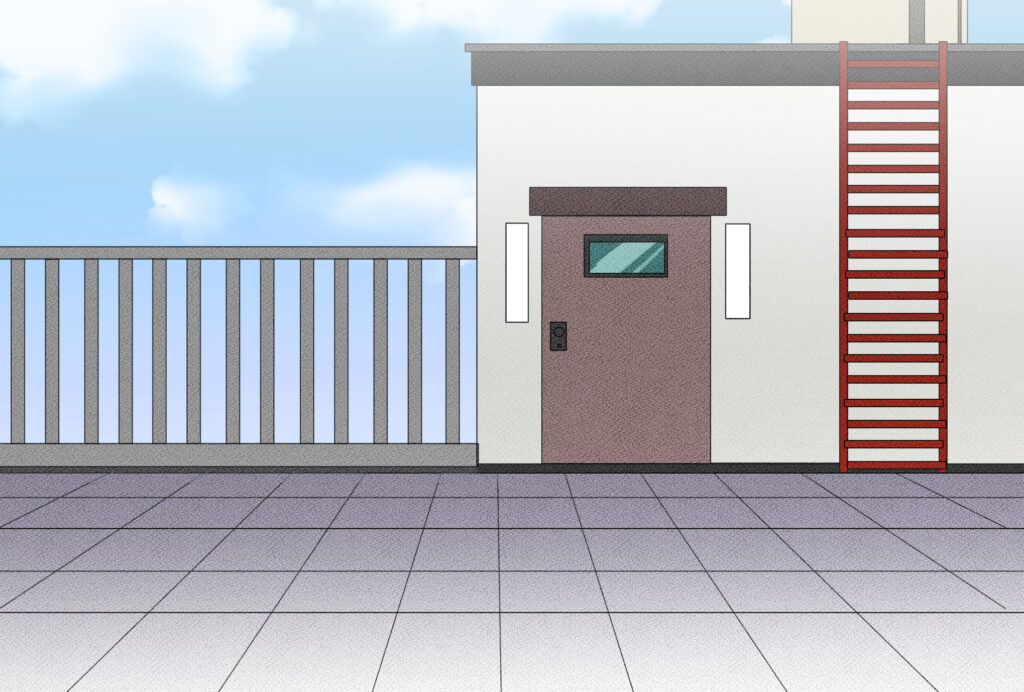

「おはよう、サキ。授業終わったんだね、起きてるよ。ちょっと考え事をしてたんだ。」
僕はワイヤレスイヤホンを外して言った。
屋上は基本的に出入り禁止だったが、古い校舎の中には一部施錠されておらず自由に出入りできる所もあった。出席があまり影響しない授業があった時や、無意味な飲み会に誘われて断るのも面倒な時、僕はよくここに来て寝転んで煙草を吸っていた。
「もうおはようの時間じゃないよ。ラクダは考え事が好きだねー。それなら哲学や心理学の授業でも出れば良いのに。一人で何かを考えててもぐるぐる頭の中を回っているだけで前に進まないでしょ。」
サキはいつものようにケラケラ笑いながら憎まれ口を叩いた。
「この前ユングって人の心理学書を読んだら集合的無意識ってものがあるって書いてあった。人間は常に普遍的な何かとは繋がっているって。だから一人で考え事をしている事も、きっと、無意味じゃない。新しい発見やひらめきはこういう時にふっと生まれたりするんだよ。」
僕は少しムキになってそう言い返したが、サキはそれを無視して無言でただ肩をすぼめるようにして笑っていた。いつものお約束のやりとりだ。
「サキも吸う?」と僕は煙草を勧めてみたが、即座に「いらない。」と言って大きくかぶりを振った。以前に思いっきり吸い込んで気分が悪くなって、丸一日寝込んだことがあったので懲りたのだろう。
それからサキは僕の隣にちょこんと座り込んだので。僕も半身を起して屋上の手すりにもたれた。そんな時、サキはよく僕の方に身体を寄せてきた。ネイビーブルーのパーカーのフードがフワッと風を起し、髪の毛からはとても良い香りがした。サキはインナーに白いTシャツを着て、カーキ色のカーゴパンツを履いていた。カチッとした服装はあまり好きじゃなかったようだ。
僕も自然とサキの肩に手を回した。息づかいや体温が直に伝わると自然と鼓動が早くなってきた。唇を重ねたい衝動にも駆られたが、煙草を吸った直後はいつも我慢をしていた。それでもサキは僕の気持ちを察してなのか「吸いたいとは思わないけど、私、煙草の匂いって嫌いじゃないよ。」とよく言っていた。
サキは真面目だったから、僕みたいに授業をサボる事はなかったが、終わった後に僕がいることを予想して、よくこの屋上まで会いに来てくれた。たいていは、授業の話や友人に対する愚痴などを勝手喋っていて、僕は適当に相づちを打って聞いているだけだったが、当時彼女以外に友達らしい友達がいなかったので、大学生活をよく知らない僕は内心ではサキの話をとても新鮮に感じていた。


サキと知り合ったのは同じ本屋でアルバイトをしていた時だった。僕の方が後から入ったが、たまたま同じ大学と言うことが解ってから、彼女の方から積極的に話しかけるようになってきた。同学年で年の近い人もいなかったので寂しかったのかもしれない。僕もサキの屈託のない明るさに惹かれて、よく話をするようになった。それから少しして僕は店長と喧嘩をしてアルバイトを辞めてしまったが、サキとはキャンパスで合うと、一緒にご飯を食べたり授業のカリキュラムを合わせて頻繁に会うようになっていた。
サキは切れ長で目が細くて、笑うとほとんど無くなってしまうくらいだったけど、とてもチャーミングだった。体格は細くて小柄だったけど、色白で頬もふっくらとしていて愛らしかった。
僕は煙草がなくなると、その箱をいつもクシャッと丸めてその辺に置く癖があった。サキはいつも、それを拾い上げてポケットに入れ「駄目だよ、ラクダ。ちゃんとゴミ箱にいれなきゃ。」といって僕を叱った。それでも煙草がなくなると「ラクダなくなっちゃったね、タスポ貸して。」と言っていつも購買まで煙草を買いに行ってくれた。
当時はお互い一人暮らしをしていたが、いつの間にか二人の部屋を行き来するような間柄になっていた。たいていは僕がサキの部屋に行くことが多かった。僕は彼女の部屋でも煙草を吸っていた。本心ではあまり良くは思っていなかったのかもしれないが、吸うときに換気扇を回したり、窓をこまめ開けて空気を入れ換えたりする事で容認してくれていた。
たまたま彼女が部屋の掃除をしていた時、本棚の本の背表紙が煙草のヤニで黄色く変色してひどく汚れている事に気がついた。彼女はその時だけは、今まで見たこともないほど悲しげで泣きそうな顔をした。そして「本が汚れるから、これからは部屋の中ではもう吸わないでね。」と言った。彼女は本当に自分の本に愛情を持っているんだなと思った。僕は誠心誠意謝罪をして、これからはベランダで吸うよと約束した。
それでも2月の大雪が降ったある日、たまたま彼女の部屋にいてベランダにも雪が積もり、外にも出るのが辛いような時があった。僕は彼女が買い物に行っている間に、煙草を吸うのを我慢できず、換気扇の下でうっかり煙草を吸ってしまった。サキは帰ってくると、煙草の匂いを敏感に感じ取り、僕が約束を破ったと言って大泣きをした。
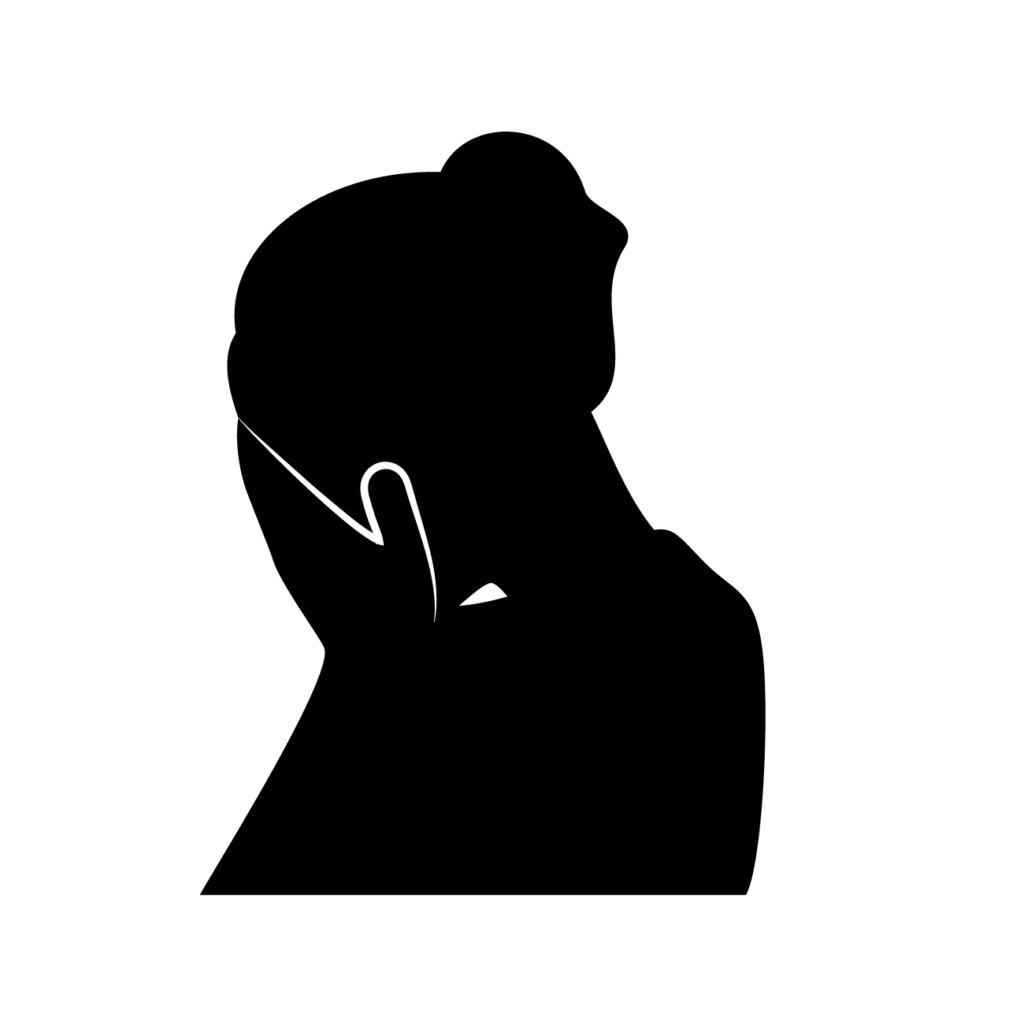
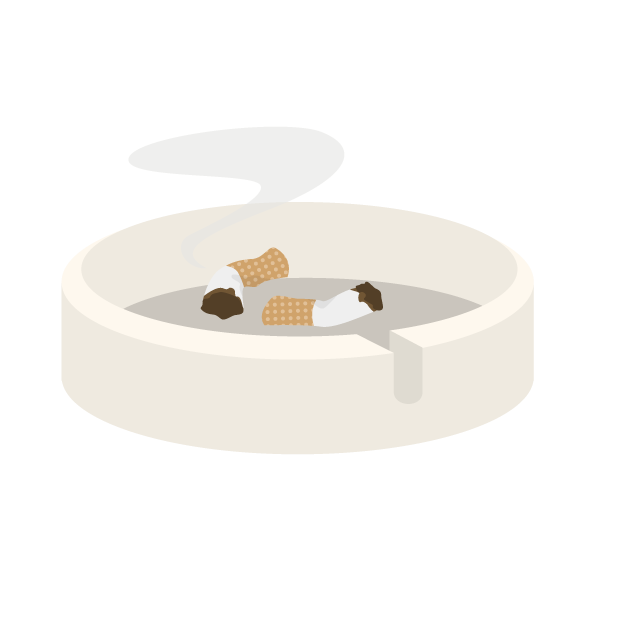
僕は事情を説明してひたすら謝った。そして換気扇の下で吸っていたので、本は汚れていないという事を何度も説明をしたが、決して許してはくれなかった。彼女は寛容な性格だったが、約束事を守るという点についてはとても頑なだったからだ。そしてもちろん他にも理由はあったが、結果的にこの事が引き金になり僕とサキは別れた。
それから僕はそこそこに単位を取りなんとか大学を卒業はしたが、サキと別れてからの大学生活はとても空虚で無意味なものになっていた。僕は失ってから初めて、自分にとってサキがどれほど大切な存在だったのかを身に沁みて感じた。
にほんブログ村
人文ランキング
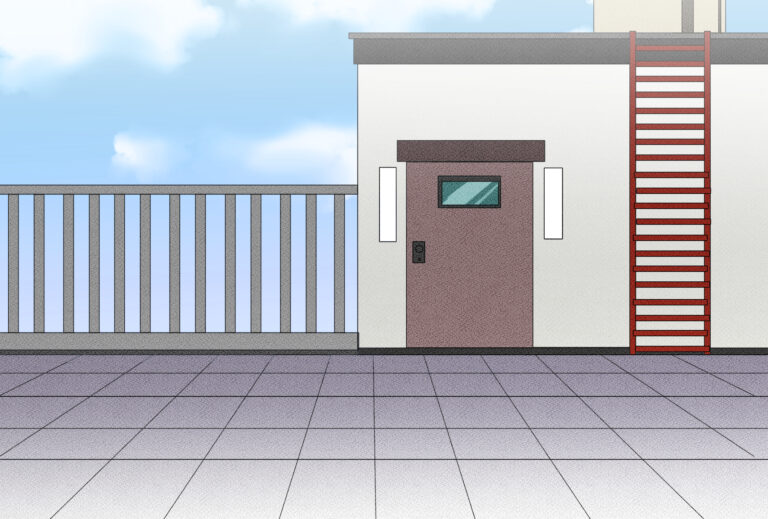


コメント