家に着いたのは9時過ぎだったが、美穂は驚いた表情で僕を出迎えた。
「どうしたの、その怪我!大丈夫?顔色も凄く悪いわよ。」
「うん、ちょっと疲れてたのかな?躓いて転んじゃってね。もう年かな、ははは。」
僕は美穂に心配をかけないように努めて明るく言った。
「そうなの?本当に大丈夫?お酒を飲み過ぎたんじゃない?顔が赤いわよ。でも、何だか変ね。お酒っていうか日焼けしたみたいな赤さね?今日は昼間外にいたの?」
僕は美穂の言葉に驚き、顔を触ってみた。確かに鼻の頭や頬にヒリヒリするような感覚があった。ビール一杯しか飲んでいないから酔いはとっくに醒めているはずだった。僕はなるべく驚きを顔に出さないようにして美穂に説明をした。
「フィールドワークがあって、日中はほとんど外で歩き回っていたんだ。そのせいかもしれないな。」
美穂は少し不審な表情を浮べたが、僕の言葉を信じてくれたようだった。
「そうだったの。それはお疲れ様。いつもデスクワークしかしていないから、余計に疲れたんじゃない?先にお風呂に入ってゆっくりする?それともご飯を先に食べる?」
「いや、悪いけど飲み会で軽く食べてきたからお腹は空いてないんだ。それから、すごく眠いんで今日はこのまま休ませてもらうよ。」
僕がそういうと美穂は更に心配そうな表情を浮べて僕を見つめたが、軽く頷いてこう言った。
「わかったわ。明日は土曜日だしゆっくり休んでね。おやすみなさい、お大事にね。」
「ありがとう。多分、一晩グッスリ眠れば明日には復活すると思う。お休み。」
それから僕は寝室に行き着ていたスーツとYシャツを脱ぎ捨て机の上に放り投げるよう置いた。ハンガーにかける気力すら残っていなかった。スウェットに着替えてベッドに潜り込むととても深い眠りがやってきた。その夜は何の夢すら見なかった。
翌朝、目覚めたのは10時過ぎだった。起き上がると体の節々が痛んだ。数年前に、ハーフマラソンを走ったことがあったが、それに匹敵するような筋肉痛だった。頭痛は多少和らいではいたが、時々、思い出したように鈍い痛みが頭を走った。やはり昨夜、僕の体に何かこの世界には無い異物のようなものが入りこみ、一度体が細胞レベルで分解されて再度組みたてられた、そんな不思議な感覚が残っていた。
それからリビングに行くと、美穂と颯太の姿はなかった。テーブルの上には美穂のメモ書きと僕のための朝食が用意してあった。
おはよう、今朝の体調はいかが?少しは回復したかしら?あまりに疲れているようなので、起しませんでした。これから颯ちゃんを連れて冬物のお洋服を買いに行ってきます。お昼を食べてから帰るので、それまでゆっくり静養していてね、お大事に。
美穂
美穂は、僕のあまりの疲れ具合を見て気を遣ってくれたようだった。僕は美穂の心遣いに感謝した。そして、用意してくれていた朝食を食べたが、食欲はほとんど湧いてこなかった。ベーコンエッグとトースト1枚をなんとか胃の中に流し込み、冷たいオレンジジュースをごくごくと飲んだ。食欲はなかったが、喉だけは以上に乾いていた。なんとなくテレビをつけていたが、何も頭に入ってこなかったので、あきらめてすぐに消した。
それから僕は、ドリップでコーヒーを淹れてから、ロフトに言ってノートパソコンの電源を入れた。しばらくの間はネットのニュースをなんとなく見ていたが、やがて書きかけだった王妃の物語の原稿を開いた。意識してそうしたわけではない。何かを書くには疲れすぎていたが、ただ何もせずにはいられなかったからだ。原稿を読み返しているうちに、ふと昨日アリゼに言われた言葉が思い浮かんだ。
「…君は気づいているか?いつまでも心の呪縛を抱えたままでいる自分自身のことを。美穂と颯汰はいつもその事を心配している。大切な家族を不安な気持ちにさせるのは良くない事だ。君はこの物語を通してそれを僕に教えてくれたじゃないか。早く解放の呪文を手に入れるんだ。そのためにまずやることはこの物語を完成させることだ…」


心の呪縛を解く、解放の呪文を手に入れる、美穂と颯太の不安を解消する、そのためにこの物語を完成させる事。それが当面向き合わなければいけない課題なのだろうか?僕は確かに過去のトラウマに囚われているのかもしれないが、本当にそんな面倒なステップを踏むことが必要なのだろうか?もっとシンプルな問題として考えれば良かった事なのに、自ら複雑な迷路ようなところに解を置いてしまったような思いがこみ上げてきた。それは砂浜にわざわざ家の鍵を放り投げて、苦労して探しているような不毛な気分だった。
そしていざ、物語の続きを書こうとすると何を書いたらいいのかさっぱり思い浮かばくなっていた。ただ昨日、アリゼに言われた事だけが残像のようにいつまでも頭の中に残っていた。
「…僕の母様の事をあまり悪者にしないで欲しいんだ。…もう、そろそろお互いに許してあげないか、母様達のことを。それに僕はもうあの人を恨んではいない。君だって本当はそうなんだろう?ただそれを認めたくないだけなんじゃないか?」
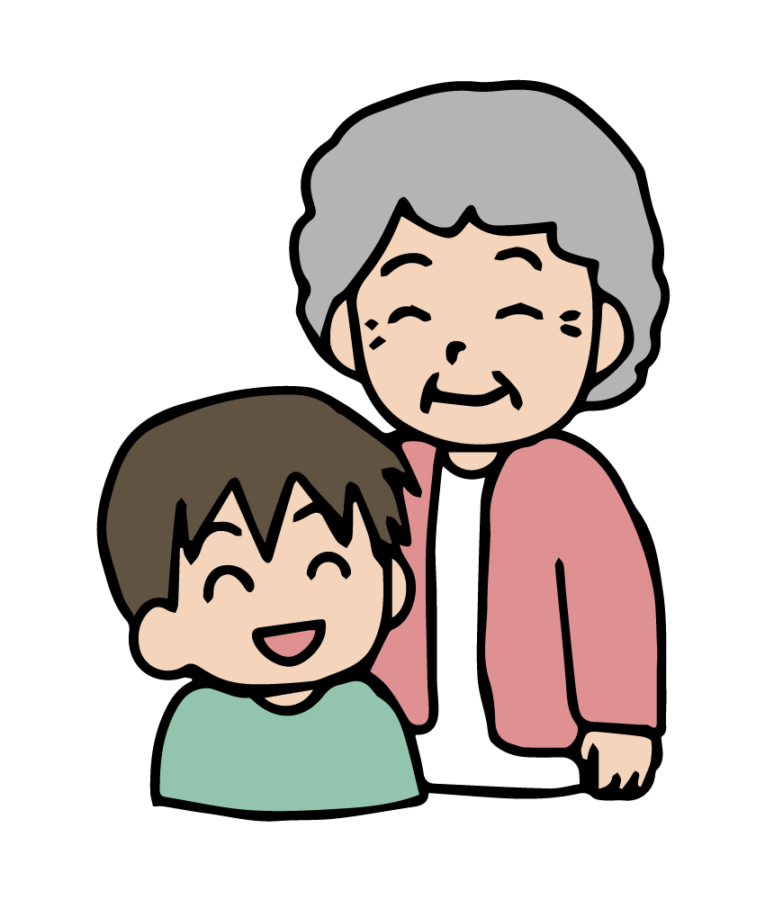

この言葉は僕が書こうとする次の物語に対して大きな影響を及ぼしていた。王妃のしてきた事は決して許されることではない。物語上でも避けては通れない内容だ。でも、アリゼの言うとおり、僕もこれ以上、王妃を悪者にはしたくなかった。それに自分の母親の事を第三者に悪く書かれたら誰だって嫌だろう。その行為を非難する権利があるとしたら、それは被害や迷惑を被った当事者だけだ。
「認めるよ、アリゼ、君の言う通りだ。君が母様を恨んでいないように、僕ももうあの人の事を恨んではいない、それが前提だ。だからこれから先の物語はリセットをしないといけない…。」
僕はそう自分に言い聞かせたが、具体的なストーリーは何も思い浮かばず途方に暮れた。
#失われた王国
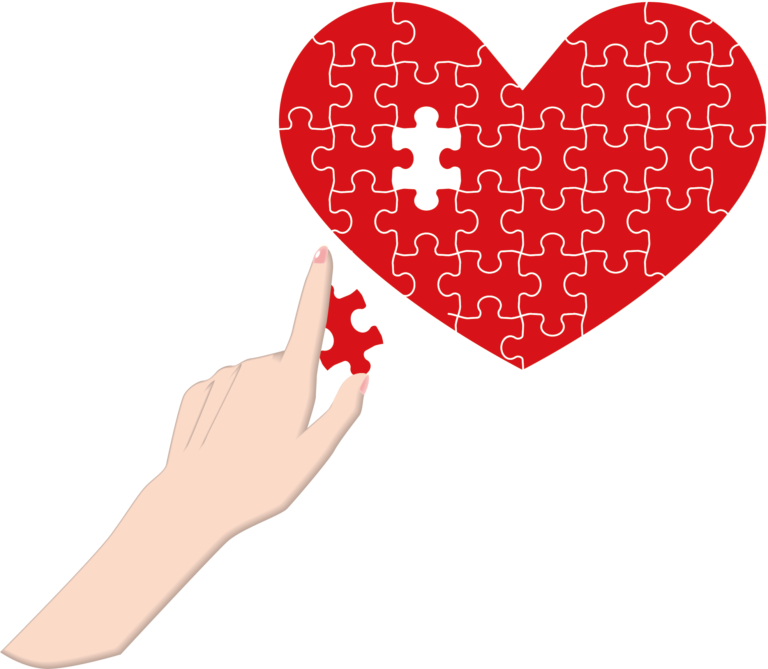

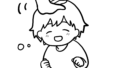
コメント