──AIと量子理論が解き明かす、死後の世界の新たな法則。四人の挑戦が今、始まる。
その日は『境界実験』の授業があった。キドは改めて説明をした。
「これは実際にお前たちが現世に干渉できるか、あるいは現世に戻ることが可能かを試みる、実践的な授業だ。成功すれば未練を完全に断ち切る助けになるかもしれん。ただしだ…」
キドは一呼吸置いてから続けた。
「成功確率は低い、限りなくだ。かの有名なロベルト・シュタインですら、現世への干渉は叶わなかった。あがいた末に、彼はすべてを手放し、ただ白い霧の向こうへ歩いていった。それを、人は”解脱”と呼ぶ。」
「ロベルト・シュタインって誰?」
修が、小声で高志に尋ねた。
「知らないのか?あの有名なノーベル賞を取った学者だよ。舌を出しておどけた写真が有名だけど見た事無いのか?」
「うん、全然知らなかったよ。」
「まぁ、俺もそれほど詳しくは知らないけど、それだけすごい人でも現世には戻れなかったってわけだ。」
高志はそう言ってため息をついた。隣を見ると修も同様に諦めの表情を浮べていた。
「だから安心しろ。この科目は”必須”だが、そんなに力を入れなくていい。どうせ、お前たちが現世に戻れることはないんだ。この授業は、ただ理論として学んでおけばいい」
キドはチョークを指で回しながら、淡々と続けた。
「ちょっと質問していいすか?」
それまで黙々と腕組みをしてキドの話を聞いていた亮司が手を上げて質問した。
「なんだ?何が聞きたい?」
「そのロベルト・シュタインさんとかが残していった記録のようなものってないんすか?」
「以前にも、同じ質問を誰かに受けた事があったな。要は参考にしたいんだろ?みんな考える事は同じだな…。答えはNOだ。この存在平面で作成したデータは、解脱の丘を超え、成仏した時点ですべて消滅する。ここにはデータの保管義務など無いんだ。もっとも君がロベルト・シュタインの残した数式を見ても理解できるとは思えんがね…。」
キドはそう言って鼻で笑った。
「そうっすね、俺なんかの頭じゃとても追っつかないっすよ。はは。」
亮司もそう言っておどけて笑った。
しかし高志は、亮司の目に浮かんだ一瞬の光を見逃さなかった。あれは…何か企んでいる目だ。
***
授業が終わると、亮司がいつもの調子で明るく声をかけてきた。
「よう、高志。今日からミッションを本格的に始めるから、あとで化学実験室にきてくれ。修も沙梨もよろしくな。」
高志は「ああ」と言って頷いてはみたが、キドの話を聞いた後でその足取りは重かった。しかし、何か引っかかるものを感じたのも事実だった。
「亮司、ちょっといいか?」
高志は廊下で亮司を呼び止めた。
「授業中、お前の表情が変わったように見えたんだが…何か気づいたことがあるのか?」
亮司は一瞬驚いたように見えたが、すぐに軽く笑った。
「鋭いな。まあ、実験室に来てくれれば分かるよ。期待していいと思うぜ」
そう言って亮司は先に歩き出した。
***
化学実験室に行くと亮司が先に席に座り、どこで入手したのかノートPCを前に何かを考え込んでいた。高志と修が入ってきたのにも気がつかないほど集中しているようだった。
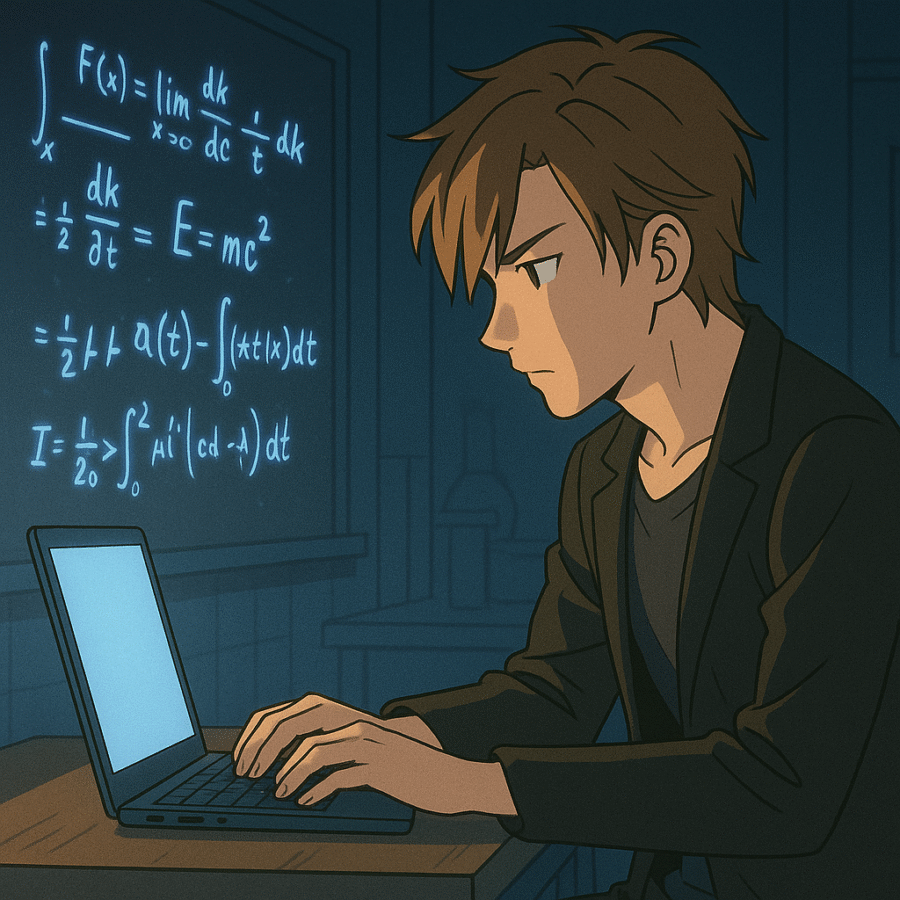
「そのノートPCどこで手に入れたんだ?」
高志が話しかけると、亮司は驚いた顔をしてこちらを見た。
「あ、気がつかなかった、すまんな、集中してたんで。このPCは、現世で俺が使っていたのと同じモデルだ。サイズの割りにはハイスペックだぜ。何しろ俺は元々プログラマーだったんたんだからな。この中では想像さえ出来れば、大抵のものは手に入る。これは凄い事だ。」
亮司は珍しく真顔で答えた。
「さてと、沙梨は?まだ来てないんだな。じゃあとりあえず3人で始めるか。」
「始めるって何を?まさかまだ現世復帰ミッションを諦めてないのか?」
高志はあきれ顔で言った。
「当然。俺は諦めてないよ。むしろ、逆境になるほど俺はテンションが上がるタイプなんだ」
「でも、天才物理学者でもできなかった事は自分には無理だって、キド先生には言ってたじゃないか。」
修も高志に同調するように亮司に言った。
亮司は二人の顔をまじまじとみて、軽いため息をついた。
「お前らは、馬鹿正直だなぁ。キドの言った事をすべて信じてるのか?『”真実”を知るためには、今まで信じてきたものなんかを、一度すべて疑ってみることから始めよう』って、どこかの哲学者も言ってたろ。」
「キドが嘘を言っているっていうのか?」
高志は驚いて亮司に尋ねた。
「ああ、少なくともロベルト・シュタインの話は嘘だ。彼の仮説と検証データはちゃんと残っていたよ、この存在平面にな。科学者ってのは自分の研究した足跡を後生に残しておきたくなるものなんだよ、次の世代のためにな。」
「どこで見つけたんだ?そしてそれは本当に信頼できるのか?」
高志は半信半疑ながらも、興味を隠せずに質問した。
「現世でいうクラウドサーバーの中だ。このPCでアクセスしているうちに見つかったよ。パスフレーズを探すのには、少し苦労したけどな。この世界が雲の上にあるとしたらまさにクラウドサーバーだ、ぴったりだな。」
高志も修も唖然として言葉を失った。
***
「でも、彼のデータが見つかったとしても、残された数式なんてとても理解できないんじゃない?彼の『次元共鳴理論』は生前でさえ、ほとんどの物理学者に理解されなかったのよ。さすがのあなたも純粋物理学なんて専門外でしょう?」
その時、遅れてやってきた沙梨が、いつになく真面目な顔をして亮司に尋ねた。高志は沙梨がロベルト・シュタインの理論まで知っていることに驚いた。
「次元共鳴理論?」
高志が尋ねると、沙梨は肩をすくめた。
「生者と死者の世界の境界が波動として共鳴する可能性を示した理論よ。でも実現には莫大なエネルギーが必要で、そのエネルギー源を見つけられなかったのが彼の最大の挫折だったって言われてるわ。」
全員が沙梨を見つめた。彼女はそれまでの屈託のない表情とは打って変わり、学者のように冷静に説明していた。
「お嬢ちゃん、なかなか物知りじゃないか」
亮司は感心したように沙梨を見た。
「ともかく、これで全員揃ったな。では、いよいよ、本論に入るが、その前にだ、前置きの話からさせてもらおう。高志、この前、コンビニで買った焼きそばパン、美味そうに食べてたよな?何でだ?もう俺達には体がないんだ。何も食わなくても生きて行ける。そうだろ?」
「…確かにそうだよ。美味かった。きっとそれは高校時代に焼きそばパンが大好きで毎日食べてたから、その頃の記憶が残ってたからじゃないかな?」
高志がそう言うと、亮司は的を得たと言わんばかりに微笑んだ。
「その通り、それは過去の経験、記憶だ。この世界でも現世で経験した事は想像力さえ働かせれば再現できる。」
「それが、ロベルト・シュタインの残したデータとどう繋がるんだい?僕には君の言いたいことがサッパリ分からないよ。」
修が頭を抱えた。
「まぁ、そう急くなって。順番に説明してやるから。つまり、現世で経験した事は想像できるということは、逆に言うと経験していないものは想像できない、この世界でも手に入れられないということだ。ロベルト・シュタインの時代には無くて、現代にあるもの、それは無数にあると思うが、最も価値のあるもの、その一つは何だと思う?これはロベルト・シュタインの仮説を紐解くのに必要なものだ。」
高志は考えてみた。もちろん、PCだってスマホだって無かっただろう。でも彼の仮説を紐解くために必要なものはそんなハードウェアじゃない。次元共鳴という考え方、波動とエネルギー…それを解析するには…
「ひょっとしてAI…量子計算が可能なAIシステム」
高志は自分の考えに驚きながら口にした。
「その通りだよ、コナン君!」
亮司は得意げに言った。
「彼の仮説をAIに解析させたら、その根本的な考え方を実に分かりやすく教えてくれたよ。シュタインの理論の核心は『意識そのものがエネルギー源になりうる』ということだ。彼が見つけられなかったエネルギー源は、実は自分自身の意識の中にあった。彼がもし、量子コンピューティングとAIと出会ってたら、きっと現世への干渉をあっさりと実現していただろう。」
「でも、そんな高度な計算が本当にできるのか?」
高志は半信半疑だった。
「もちろん、通常のAIじゃ無理だ。でも俺はこの世界の特性を利用した特殊なシステムを構築した。量子もつれの原理をこの存在平面の法則と組み合わせることで、シュタインの理論を実用化できる可能性が見えてきたんだ。」
亮司の目は輝いていた。
「実は俺はAIエンジニアもやっていた。まぁ、それでもどこまで行けるか分からんが、ちょっとは楽しくなってきただろ?」
高志は唖然として、亮司の言葉を聞いていた。その瞬間、胸の奥に、久しく感じなかった「鼓動」のようなものが宿った。希望。今ここにある、確かな、希望だった。
「僕たちは、具体的に何をすればいいの?」
修が前のめりになって尋ねた。彼の目にも光が戻っていた。
「まずは各自の未練の本質を明確にする必要がある。それから意識を集中した状態で波動共鳴実験を行う。高志と修は身近な人への想いが強いから、具体的なターゲットがすでにある。それが良い起点になるはずだ。」
「天才物理学者とプログラマーの融合か…。なかなかロマンチックな組み合わせね。」
「期待してるわよ。……でも、失敗しても笑ってあげる。」
沙梨は腕組みをしながら楽しげに言った。沙梨の言葉を聞いて亮司は、珍しく照れくさそうな顔をして笑った。
「さて、これから本格的に始めるぞ。高志、修、それに…沙梨も。これから具体的なプランと役割分担の説明をさせてもらう。キドの『境界実験』の授業が終わるまでにプログラムを完成させなきゃならないからな。」
亮司の声には確信があった。高志は、この奇妙な天才プログラマーを信じてみようと思った。途方もない計画かもしれないが、それは娘の紬に会う唯一の望みでもあった。
たった一度でも会えるなら。たった一言、“ごめん”と伝えられるなら──それだけでもいい。
「OKだ。やろう、その実験を」
高志の声は、久しぶりの決意に満ちていた。
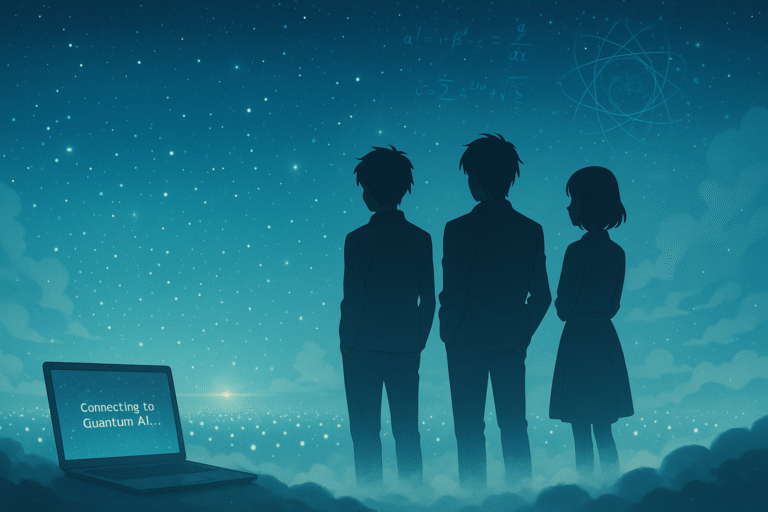


コメント